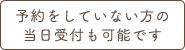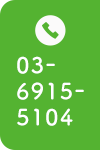「どこまでが加齢の“うっかり”で、どこからが病気なの?」という疑問に答えるため、段階ごとに読み進められる道しるべを用意しました。ご自身がどこに当てはまるかを確認し、次のステップをご覧ください。
- ① 物忘れとは(総論)
- ② 加齢による物忘れ
- ③ MCI(軽度認知障害)
- ③ 認知症
- ④ 代表的な認知症のタイプ
- ⑤ 治療・対応の選択肢
- ⑥ ご相談ください
物忘れとは(総論)
まず知ってほしいこと
- 加齢に伴う「うっかり」と、病気による認知症は違います。
- 見分け方の軸は、日常生活に支障が出ているかどうか。
- 支障が出ていない場合は「加齢」やMCI(前段階)であることも。早めの評価で対応の選択肢が広がります。
加齢による物忘れ
特徴
- 人名・単語が出づらいが、ヒントがあれば思い出せる。
- 予定や持ち物をメモやスマホで補えば普段通りに暮らせる。
- 「置いた場所を忘れる」はあるが、体験自体を丸ごと忘れることは少ない。
心配が続く場合は、次の段階のMCIも確認しましょう。
MCI(軽度認知障害)
「正常」と「認知症」のあいだ
- 生活はほぼ自立しているが、検査で客観的な低下が見える状態。
- 時に体験した出来事そのものを忘れてしまうことがある。
- 全員が認知症になるわけではないが、進行リスクが高いグループが含まれる。
- 運動・食事・睡眠・社会活動で改善が期待でき、定期チェックが大切。
- アルツハイマー病理(アミロイド陽性)があるアルツハイマー病によるMCIでは、抗Aβ抗体薬による治療の対象になり得ます。
くわしい内容や検査・対応は、この下の既存セクションに続きます。
認知症とは
特徴
- 日常生活に支障が出ている状態が「認知症」と呼ばれます。
- 記憶だけでなく、注意力・言語・判断力・行動など複数の機能が影響を受けることがあります。
- 進行性の変性疾患や血管障害が主な原因ですが、治療で改善できる「可逆性認知症」もあります。
- 早期に診断し、治療や支援を組み合わせることで、進行を遅らせ生活の質を保つことが可能です。
- 運動・食事・睡眠・社会活動による生活習慣の改善は、認知症でも大切です。
- アルツハイマー型やレビー小体型では、従来の抗認知症薬(内服薬)が有効な場合があります。
- さらに、軽度のアルツハイマー型認知症では、抗Aβ抗体薬による治療が適応となる場合もあります。
次に、代表的な認知症のタイプを見ていきましょう。
代表的な認知症のタイプ
分類の考え方(患者さん向けに簡潔に)
- 変性性認知症(脳の神経細胞にたまるタンパク質が主因)
- アルツハイマー型(AD):もっとも多い。新しい記憶が苦手に。
- レビー小体型(DLB):認知のゆらぎ・幻視・手足がこわばる。
- 前頭側頭型(FTD):性格や行動の変化、ことばの障害。
- 嗜銀顆粒性(AGD):超高齢に多く、ゆっくり進行。
- 血管性認知症(VaD)(こちら) :脳梗塞や小さな出血・白質病変が関係。階段状に悪化しやすい。
同じ方にいくつかのタイプが重なることも珍しくありません(混合型)。
可逆性認知症
代表例とチェック項目
| 原因 | 所見のヒント | 検査 | 治療 |
|---|---|---|---|
| 正常圧水頭症(iNPH) | 歩行障害・尿失禁・認知低下(三徴)。磁石歩行。 | MRIで側脳室拡大、DESH所見。髄液タップテスト。 | シャント術で改善が期待。 |
| 甲状腺機能低下症 | 易疲労・体重増加・寒がり・浮腫。 | TSH/FT4。 | ホルモン補充。 |
| ビタミン欠乏(B12/葉酸) | しびれ・貧血・うつ様症状。 | 血算、B12、葉酸。 | 補充療法。 |
| 薬剤性(抗コリン薬・ベンゾ等) | 開始/増量と同期した注意低下・ふらつき。 | 服薬レビュー。 | 減量・中止の検討。 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 日中傾眠・いびき・無呼吸の目撃。 | 睡眠検査。 | CPAP、減量、鼻治療。 |
| うつ病(仮性認知症) | 意欲低下・自己評価の低さ・朝方不調。 | 抑うつ評価、経過観察。 | 抗うつ療法、心理社会的支援。 |
| 感染・炎症・その他 | 甲状腺炎、梅毒/HIV、自己免疫脳炎、慢性硬膜下血腫、肝腎障害など。 | 採血・画像・必要時髄液。 | 原因治療。 |
まずは可逆性の要因を丁寧に除外・治療します(例:慢性硬膜下血腫は手術で改善することがあります)。
治療・対応の選択肢(段階別ダイジェスト)
認知機能の段階(MCI/軽度認知症/中等度以上)と、 原因となる病気(アルツハイマー病/レビー小体病)によって、 適応となる治療は異なります。
ここでは、現在行われている代表的な治療を 「どの段階で、どの病気に使われるか」という視点で整理します。
治療適応の全体像(段階 × 原因疾患)
※ アルツハイマー病の場合
- MCI:疾患修飾療法(抗Aβ抗体薬)のみ
- 軽度認知症:抗Aβ抗体薬+従来の内服薬
- 中等度以上:従来の内服薬のみ
※ レビー小体病の場合
- 軽度認知症以上:従来の内服薬
- 抗Aβ抗体薬は適応なし
| 段階 | アルツハイマー病 | レビー小体病 |
|---|---|---|
| MCI | 抗Aβ抗体薬:○ 従来の内服薬:- |
従来の内服薬:- 抗Aβ抗体薬:- |
| 軽度認知症 | 抗Aβ抗体薬:○ 従来の内服薬:○ |
従来の内服薬:○ 抗Aβ抗体薬:- |
| 中等度以上 | 従来の内服薬:○ 抗Aβ抗体薬:- |
従来の内服薬:○ 抗Aβ抗体薬:- |
※ 抗Aβ抗体薬は、アルツハイマー病が原因であること (アミロイドβ陽性の確認など)が前提となります。
① 生活習慣と合併症の整え(すべての段階で共通)
- 運動・食事・睡眠・社会活動の見直しは、 MCIから認知症まですべての段階で重要な治療の土台です。
- 難聴、抑うつ、睡眠障害、視力低下などを治療することで、 「認知症が悪化したように見えていた状態」が改善することがあります。
② 疾患修飾療法(抗Aβ抗体薬)【アルツハイマー病:MCI~軽度】
- レカネマブ/ドナネマブ: アルツハイマー病によるMCI~軽度認知症が対象。
- 治療開始前にアミロイドβ陽性の確認が必要です。 治療中はMRIによるARIAの監視を行います。
- 症状を改善する治療ではなく、 病気の進行をゆるやかにすることを目的とします。
※ ARIA(アミロイド関連画像異常)とは、 脳のむくみや小さな出血などが起きていないかを MRIで確認する安全管理項目です。
③ 従来の内服薬(対症療法)【軽度認知症以上】
- コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル等)、 メマンチンは認知機能や生活機能を支えます。
※ 高齢者では慎重な判断が必要
- 効果が限定的になる一方で、副作用の影響が大きくなります。
- 食欲低下、体重減少、徐脈、転倒、眠気、せん妄などが問題となることがあります。
- そのため、使用しない・減量・中止を選択することも治療の一部です。
生活習慣、合併症管理、安全対策、家族支援、意思決定支援など、 すべての段階で共通して重要な内容は 治療・ケアの基本 にまとめています。
診断の流れ
評価と検査
- 問診・情報提供:発症時期、経過、日常の困りごと、睡眠・幻視・転倒、薬剤歴。
- 認知機能検査:MMSE、HDS-R、MoCA、FAB、語流暢性検査など。
- 画像検査:頭部MRI、必要に応じて脳血流SPECT。
- 鑑別のための採血:甲状腺・B12/葉酸、炎症・感染、代謝。
- (必要時)バイオマーカー:アミロイドPET/髄液、血液Aβ関連検査(いずれも特殊検査です)。
代表的な認知症
認知症には大きく分けて、脳の神経細胞がゆっくり変性していくタイプ(変性性認知症)と、 脳の血管の障害に伴って起こるタイプ(血管性認知症)があります。
変性性認知症にはアルツハイマー型(AD)・レビー小体型(DLB)・前頭側頭型(FTD)・嗜銀顆粒性(AGD)などが含まれます。
一方で血管性認知症(VaD)は変性性ではありませんが、臨床でよくみられる代表的な認知症であり、ここに併せて解説します。
アルツハイマー型認知症(AD)
特徴
- 初期から新しいことを覚えにくい(エピソード記憶障害)が目立つ。
- 時間→場所→人物の順で見当識障害が進みやすい。
- 進行に伴い、言語・視空間認知・実行機能も低下。
画像/補助所見
- MRIで内側側頭葉(海馬)萎縮、側頭頭頂連合野の萎縮。
- SPECTで頭頂・側頭連合野の血流低下。
薬物療法(対症)
- コリンエステラーゼ阻害薬:ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン。
- NMDA受容体拮抗薬:メマンチン。
病期・副作用を見ながら個別最適化します。
疾患修飾療法(初期例で適応)
- アルツハイマー病によるMCI~軽度アルツハイマー型認知症の段階では、抗Aβ抗体薬(レカネマブ:レケンビ®/ドナネマブ:ケサンラ®)による治療が保険適用です。
- 実施にはアミロイド陽性(PET/髄液/血液バイオマーカー等)の確認と、MRIでのARIA監視など安全管理が必要です。
- ARIAは「脳のむくみや小さな出血」が画像で見つかる副作用の総称です。多くは軽症・一過性で経過観察になりますが、頭痛・ふらつきなど気になる症状が出たらすぐご連絡ください。
- 効果は進行速度の抑制であり、症状を元に戻す治療ではありません。生活介入(運動・食事・睡眠・社会参加)との併用が重要です。
- 詳しくは下記「疾患修飾療法(抗Aβ抗体薬)」をご覧ください。当院で適応評価と連携調整を行います。
レビー小体型認知症(DLB)
中核症状
- 注意・覚醒レベルの変動、具体的な幻視、パーキンソニズム、レム睡眠行動異常(RBD)。
画像/補助所見
- SPECTで後頭葉(視覚連合野)血流低下。
- 心筋MIBGシンチの集積低下が診断補助。
治療と注意点
- ドネペジルが日本で適応。認知・幻視に有効なことがあります(個人差があります)。
- 抗精神病薬過敏:定型・一部非定型で重篤副作用の恐れ。極力回避し、必要時は専門医管理・最少量で。
- 抗パーキンソン病薬は幻覚・妄想が悪化する場合があり、使い方に注意が必要です。
前頭側頭型認知症(FTD)
臨床型
- 行動変異型(bvFTD):脱抑制、常同行為、共感性低下、食嗜好変化。
- 原発性進行性失語(PPA):意味変異・非流暢/文法性変異・ロゴペニック変異。
画像/補助所見
- MRIで前頭葉・側頭極の左右非対称な萎縮、SPECTで前頭側頭血流低下。
治療のポイント
- 中核改善効果は限定。SSRI等で行動症状緩和を図る。
- 作業・言語療法、環境調整、介護者支援が中心。
- 一部で遺伝的要因(例:MAPT、GRN、C9orf72)が関与します。家族歴が気になる場合はご相談ください。
嗜銀顆粒性認知症(Argyrophilic Grain Disease: AGD)
特徴
- 超高齢発症(80歳前後に多い)、緩徐進行。
- 辺縁系優位のタウオパチー。しばしば他病理(ADなど)と混在します。
画像/対応
- MRIで内側側頭葉萎縮が目立つことも。確定診断は困難。
- 対症療法と生活機能の維持を重視。過鎮静・多剤併用を回避。
血管性認知症(VaD)
特徴
- 脳梗塞・微小出血・白質病変などの血管障害が原因。
- 階段状の悪化や遂行機能低下・歩行障害・感情失禁が目立つ。
- ADとの混合型も多く、両方に対する対応が必要なことがあります。
画像/補助所見
- MRIでラクナ梗塞、深部/皮質下白質病変、微小出血。
治療のポイント
- 二次予防:降圧・糖脂質管理・抗血小板薬の適正化・禁煙・運動など生活習慣病の管理が最重要です。
- 混合型ではAD治療薬併用を検討。
主要疾患の鑑別表
主要症状の比較
| 疾患 | 初期の主症状 | 特徴的サイン | MRI/機能画像 | 薬物反応・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| アルツハイマー型(AD) | 新しい記憶が保てない(記銘力低下) | 時計描画・言語想起の低下、見当識障害 | 海馬・側頭頭頂萎縮、連合野血流低下 | ChE阻害薬/メマンチン有用。抗コリン薬は避ける。 |
| レビー小体型(DLB) | 注意の変動、見え方の異常、転倒 | 具体的幻視、RBD、パーキンソニズム、MIBG低下 | 後頭葉血流低下、海馬萎縮は軽度〜不均一 | ドネペジル適応。抗精神病薬過敏に要注意。 |
| 前頭側頭型(FTD) | 人格・社会性の変化/言語障害 | 脱抑制、常同行為、食嗜好変化;PPA各亜型 | 前頭・側頭極の左右非対称萎縮 | ChE阻害薬の効果限定。SSRI等で行動症状緩和。 |
| 血管性(VaD) | 階段状悪化、遂行機能低下、歩行障害 | 感情失禁、局在徴候、脳血管危険因子 | ラクナ梗塞・白質病変・微小出血 | 二次予防が柱。混合型ではAD薬併用を検討。 |
| 嗜銀顆粒性(AGD) | 緩徐な記憶低下、実行機能の軽度低下 | 超高齢発症、混合病理の併存が多い | 内側側頭葉優位の萎縮(変動) | 対症療法中心。多剤投与・過鎮静を避ける。 |
※同じ方でも病理の混在は珍しくありません。定期評価で方針を調整します。
疾患修飾療法(抗Aβ抗体薬)
概要
- アルツハイマー病の原因蛋白アミロイドβ(Aβ)を標的とし、脳内Aβを除去して進行を緩やかにすることを目指す点滴薬。
- アルツハイマー病によるMCI〜軽度アルツハイマー型認知症が対象。アミロイド陽性の確認(PETまたは髄液バイオマーカー)が前提。
- 代表薬:レカネマブ(レケンビ®)、ドナネマブ(ケサンラ®)(国内ではMCI/軽度ADに保険適用)。
導入までの流れ
- 診断確証:臨床評価+MRI、必要に応じてSPECT。
- バイオマーカー:Aβ陽性の確認(PET/CSF/血液)。
- リスク評価:APOE ε4(保因でARIAリスク高)、抗凝固薬内服、微小出血の既往など。
- 共有意思決定:効果の大きさ・通院負担・副作用(ARIA)を丁寧に説明。
投与とモニタリング
- 点滴投与(通常2~4週ごと)。スケジュールは薬剤で異なる。
- MRIモニタリング:導入前、初期(例:3か月・6か月)および症候時に実施し、ARIA(Aβ関連画像異常:脳のむくみや小さな出血)を監視。
- 注意症状:新規の頭痛・意識変容・めまい・視覚症状・けいれん。出現時は速やかに連絡+評価。
適応外・慎重投与の目安
- 中等度〜高度の認知症、制御不良の出血傾向、広範な微小出血や表在性鉄沈着。
- 抗凝固薬使用中は原則慎重(出血リスク評価が必須)。
期待できる点・限界
- 認知・機能低下の速度を抑制するエビデンス。
- 症状を元通りに回復させる治療ではないため、早期導入と生活介入の併用が重要。
- 治療に伴う不安や負担感がある場合は、ご家族・医療者と一緒に気持ちのケアも行います。
当院では、適応の有無を評価し、必要に応じて連携施設でのバイオマーカー検査・導入を調整します。
治療・ケアの基本
共通の方針(どの段階でも大切)
- 生活習慣(脳と血管を守る)
有酸素運動(歩行など)・筋力トレーニング、地中海食/DASH寄りの食事、社会参加、十分な睡眠を整えます。
生活習慣はMCIから認知症まで共通して効果が期待できる「土台」です。 - 合併症の見直し(「認知症のように見える」状態を減らす)
難聴・視力低下・抑うつ・睡眠障害は、認知機能の低下を強く見せたり、日常生活の困りごとを増やします。
治療や補聴器・眼鏡の調整で、認知の見え方が改善することがあります。 - 薬物療法は「少量から・定期的に見直す」
体重減少、ふらつき、せん妄、徐脈などの副作用が出やすいため、開始後も効果と副作用をセットで評価します。
抗コリン作用のある薬(一部の睡眠薬、抗アレルギー薬、過活動膀胱治療薬など)は認知に影響することがあるため、原則回避または減量を検討します。 - 安全(転倒・事故)を最優先に
転倒は入院や寝たきりのきっかけになり、認知症の進行を早めることがあります。
家の環境調整(段差・手すり・照明)、歩行補助具の検討、薬の整理などでリスクを下げます。 - 家族・介護者支援(長く続くケアの要)
介護負担の軽減、サービス連携(ケアマネ・訪問看護・デイ等)、困りごとの見える化を行います。
ご本人の希望を中心に、家族と一緒に現実的なケアプランを作ります。 - 意思決定支援(将来の見通しを共有)
「今できること」と「今後起こり得ること」を整理し、ご本人の価値観に沿って治療・生活の方針を決めます。
運転、仕事・家計管理、同居・介護体制など、早めに話し合うほど選択肢が広がります。
※治療は「薬だけ」で決まるものではありません。生活・合併症・環境・支援を整えることで、症状と生活の質(QOL)を大きく改善できることがあります。
生活習慣の目安(まずはここから)
- 運動:週3〜5日、合計150分/週を目標(早歩きなど)。可能なら週2回の筋トレも。
- 食事:野菜・豆・魚・ナッツ・オリーブオイル中心、塩分と加工食品・甘い飲料を控えめに。
- 睡眠:7時間前後を目安。いびき・無呼吸が疑われる場合は評価します。
- 社会参加:会話、趣味、ボランティア、学習など「人と関わる活動」を継続。
合併症チェック(よくある見落とし)
- 難聴:補聴器の導入で会話量が増えると、認知の負担が減ります。
- 視力:白内障・緑内障などの治療で生活が安定することがあります。
- 抑うつ:意欲低下や集中力低下が「物忘れ」に見えることがあります。
- 睡眠障害:不眠、睡眠時無呼吸、レム睡眠行動障害などを評価します。
- 薬剤:抗コリン作用薬、鎮静系の薬、アルコールの影響を見直します。