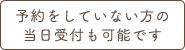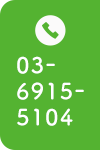頭痛について
 頭痛は日常的によく起こる症状です。 よくある頭痛の大半は一次性頭痛と呼ばれる基礎疾患のない頭痛で命に関わる症状ではありませんが、症状が強い場合は寝込んでしまい日常生活や仕事に支障をきたすこともあります。 一方で脳の疾患が原因で生じる二次性頭痛もあります。二次性頭痛の中には緊急性の高い疾患が含まれますので注意が必要です。 いつもとは様子が違う頭痛がある・次第に痛みが強くなる頭痛・頭痛が長期間継続して治まらない・立っていられないほどの激しい頭痛がある場合は、緊急性の高い疾患による頭痛の可能性があります。 どうぞお気軽に当院までご相談ください。命に関わる頭痛ではないことを検査ではっきりとさせてから、頭痛のタイプ別に対処法をご相談いたします。 万が一、緊急性を要する病状であった場合は、責任を持って救急医療機関と連携をとってご紹介いたします。
頭痛は日常的によく起こる症状です。 よくある頭痛の大半は一次性頭痛と呼ばれる基礎疾患のない頭痛で命に関わる症状ではありませんが、症状が強い場合は寝込んでしまい日常生活や仕事に支障をきたすこともあります。 一方で脳の疾患が原因で生じる二次性頭痛もあります。二次性頭痛の中には緊急性の高い疾患が含まれますので注意が必要です。 いつもとは様子が違う頭痛がある・次第に痛みが強くなる頭痛・頭痛が長期間継続して治まらない・立っていられないほどの激しい頭痛がある場合は、緊急性の高い疾患による頭痛の可能性があります。 どうぞお気軽に当院までご相談ください。命に関わる頭痛ではないことを検査ではっきりとさせてから、頭痛のタイプ別に対処法をご相談いたします。 万が一、緊急性を要する病状であった場合は、責任を持って救急医療機関と連携をとってご紹介いたします。
一次性頭痛
基礎疾患のない頭痛です。 片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛が含まれます。繰り返し起こる頭痛で、国民の3人に1人が悩んでいると言われています。 もっとも頻度が高いのは、緊張型頭痛ですが、病院やクリニックを受診する方の中では片頭痛が多くなります(60~80%)。 群発頭痛はかなりまれな頭痛です。
片頭痛
多くの場合片側、時には両側の頭部に、ズキンズキンと響く拍動性の非常に強い痛みが生じます。 痛む頻度は人それぞれです。 ただし、片側性や拍動性は片頭痛診断のために必須の症状ではありません。 一度痛みが出ると、4〜72時間ほど続きます。ギザギザした光が見えたり、視野が狭くなるなどの前兆を伴ったりすることもあります。また、吐き気や嘔吐を伴うこともあり、寝込んでしまい日常生活や仕事に支障をきたす人も多くいます。片頭痛は、女性に多く見られるのも特徴です(男:女=1:4)。
そんなつらい頭痛の代表となる「片頭痛」ですが、一般での認識は低く、市販薬でまぎらわすとか、ただ我慢して嵐が過ぎるのを待つという対応をしている方が多いようです。片頭痛発作が慢性化してくると、本来の特徴が徐々に消えてなくなり、持続性のダラダラした頭痛に変化していくことも少なくありませんので緊張型頭痛と間違われることも少なくありません。 その結果、鎮痛薬の使い過ぎによって痛みを感じる脳内の神経回路が変調をきたして、痛みを感じる中枢が過敏になり、ますます日常的に繰り返す「慢性的な頭痛」(薬物の使用過多による頭痛)になっていきます。
片頭痛はただ頭の片側が痛くなるだけのもので我慢するしかないと考えてはいけません。 頭痛の起こる仕組みがかなり解明されている、れっきとした疾患です。 この数年間で片頭痛に対する投薬治療の選択肢が驚くほど広くなっており、治療薬の有効性も高まっています。 当院では適切な対応を見つけて治療していくことで、慢性的な頭痛から抜け出して、生活の質を向上していけるようお手伝いいたします。
片頭痛の原因
片頭痛は視床下部から始まった脳細胞の異常な活性化が広がって、脳の周囲を覆っている硬膜周辺の血管に分布する三叉神経終末を興奮させて、CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)などの血管作動物質が放出されることで起きます。 放出された血管作動物質が硬膜周辺の血管壁に結合すると、硬膜周辺の血管拡張、血漿タンパクの漏出、肥満細胞からのヒスタミンの遊離などが起こり血管周囲に神経原性炎症を引き起こします。 その刺激が三叉神経終末から脳幹にある三叉神経核に至り、嘔気・嘔吐や自律神経系の活性化が生じます。さらに刺激が視床を経由して大脳に伝わり、痛みとして自覚されることになります。
視床下部から始まった細胞の異常な活性化が三叉神経終末を興奮させる前に脳の他の領域での神経活動にゆらぎを与えると、前兆と呼ばれる症状が頭痛発作の前に起きることになります。 前兆の中でもっともよく起きるのは、後頭葉での脳活動のゆらぎが原因で起きる視覚症状(視界がぼやける・光の閃光やジグザグ模様が見える・一部の視野が欠ける、など)で閃輝暗点と呼ばれます。
片頭痛の症状
予兆期: あとで述べる前兆や頭痛発作が起こる数日前から、食欲の亢進・倦怠感・あくび・感覚系の機能亢進・体液貯留などの変調が起きることが多く、予兆と呼ばれています。このときには、視床下部が異常に活性化されつつあります。
前兆期: 頭痛発作の起きる 30 分から 1 時間前に生じる症状です。必ず起きるわけではなく、前兆はない方も多いです。
● 視覚症状:視界がぼやける。光の閃光やジグザグ模様が見える。一部の視野が欠ける、など
● 感覚症状:手や顔、体の一部にチクチクするような感覚
● 言語症状:言葉が出てこない
● 運動症状:力がはいらない
● 脳幹症状:めまい、平衡障害、意識低下や混乱状態
● 網膜症状:片目だけに視覚異常が生じる
頭痛期:脈打つような強い痛みが出現。効果的な薬物を使わなければ、通常 4 時間から 72 時間続きます。辺縁系や視床下部の刺激症状として、悪心・嘔吐、光・音過敏などを伴います。
回復期:眠気・食欲低下・疲労感・うつ状態・躁状態などが見られます。
片頭痛の誘因
片頭痛のサイクルに入ってしまうきっかけを作る誘因はいろいろと知られています。 ストレスや睡眠不足などがありますが、ストレスからの解放や睡眠過多も誘因になります。 月経周期、人混み、強い臭い、強い光、激しい運動がきっかけになる方もいます。 気圧の変化・温度差で片頭痛が誘発される方も多いと思います。 空腹・脱水もきっかけになります。 人によってはチーズ・チョコレートを食べた後に片頭痛が誘発される方もいます。 アルコール飲酒もきっかけになります。
片頭痛の薬
一般的に使用される鎮痛薬の他に、片頭痛発作が出現したときに内服して片頭痛を軽減させる急性期治療薬と、片頭痛発作が頻回に起こる場合に毎日続けて服用することによって片頭痛発作の頻度や強さを抑える予防薬とがあります。
鎮痛解熱薬(NSAIDs:非ステロイド性抗炎症薬)
アスピリン、バファリン、イブ、ロキソニン、ボルタレン、ブルフェン、ナイキサンなどです。いずれも片頭痛に特化した薬ではなく、一般的な疼痛や発熱に対して使用する薬です。NSAIDsを長期に内服した場合、胃潰瘍、腎障害、喘息などの副作用を引き起こすことがありますので要注意です。カロナールは、NSAIDsと同列に扱われることも多いのですが、厳密にはNSAIDsではなく副作用が少なく使いやすい薬です。
市販の鎮痛薬には、鎮痛効果を高めるためにカフェインや鎮静剤が配合されているものも多く、依存性が問題になることもあるので注意が必要です。
急性期片頭痛治療薬
トリプタン製剤(セロトニン1B/1D受容体を介して、CGRPの放出を抑制する)
イミグラン®、ゾーミック®、レルパックス®、マクサルト®、アマージ®の5種類が日本では発売されています。 いずれもセロトニン1B受容体に作用して拡張した血管を収縮させます。 また、セロトニン1D受容体に作用してCGRPの放出を抑制し、神経原性炎症を抑えて痛みを軽減します。片頭痛に特化した薬で効果は高いと言えます。 ただし、服用するタイミングが難しいのが弱点です。早く飲み過ぎれば、トリプタンが消えてしまいCGRPが放出されてしまうこともあるし、実はそのあとに頭痛発作が起きない場合もあります。 遅ければCGRPが放出されてしまい効果がありません。トリプタン製剤も飲みすぎれば薬剤乱用性頭痛を引き起こす可能性があります。 また、血管収縮作用があるため脳卒中や心筋梗塞の既往がある方には使用を控えるようにとされています。 トリプタン製剤内服後に、胸部圧迫感・息苦しさを感じることがありますが1B受容体に関連した一過性の症状なので心配しなくて大丈夫です。
ジタン製剤(セロトニン1F 受容体を介して、CGRP の放出を抑制する)
2022年にレイボー®が日本で発売となりました。 セロトニン1F 受容体は、脳の中に広く分布していて活性化されると、三叉神経からの痛みの信号が伝わりにくくなります。 レイボーは血液-脳関門を通過して脳内に到達できるので脳内のセロトニン1F 受容体に作動します。 血管収縮作用がないので脳卒中や心筋梗塞の既往がある方にも安心して使えます。 また、トリプタン製剤に比べて服用のタイミングが遅れても効果が高いと報告されており、有用性が高い薬です。
ただし、眠気やだるさが出やすい薬です。 最初は、夜間や休みの日に試してみることをお勧めします。副作用は 4 時間くらいでおさまります。 最初副作用が出ても、だんだん慣れてくることも多いようです。
服用の方法は、①トリプタン製剤の効果がいまひとつのときに追加で服用する、②トリプタン製剤の代わりに最初から服用する、③トリプタン製剤と一緒に服用する、などが選択肢になります。 新薬なので後発品がすでに発売されているトリプタン製剤と比べると3倍くらいの値段です。
トリプタン製剤
| イミグラン®(スマトリプタン) |
錠剤・点鼻薬・注射 |
|---|---|
| ゾーミッグ®(ゾルミトリプタン) | 錠剤・口腔内崩壊錠(水なしで飲めるお薬) *1回1錠:2時間あけて1錠追加可、1回2錠も可で1日最大4錠 ゆっくり効いてゆっくり切れるお薬です。 |
| レルパックス®(エレトリプタン) | 錠剤 *1回1錠:2時間あけて1錠追加可、1回2錠も可だが1日最大2錠 早く効いてゆっくり切れるお薬です。 副作用は比較的少ないです。 |
| マクサルト®(リザトリプタン) | 錠剤・口腔内崩壊錠(水なしで飲めるお薬) *1回最大1錠:2時間あけて1錠追加可 早く効いて早く切れるお薬です。 |
| アマージ®(ナラトリプタン) | 錠剤 *1回最大1錠:4時間あけて1錠追加可 ゆっくりと効きますが、長く効くお薬です。 |
ジタン製剤
| レイボー®(ラスミジタン) | 錠剤(1回50mg~200mg適宜増減可、1日最大200mg) 2022年発売の新薬なので薬価は高い。 血管収縮作用がない。 内服のタイミングが遅れても効果がある。 |
|---|
片頭痛予防薬
発作が頻回であったり(月に3-4回以上)、症状が重かったり、副作用で急性期治療薬が飲めなかったりする場合は、片頭痛予防効果のある薬を毎日飲むことを検討します。
鎮痛解熱薬や急性期片頭痛治療薬を月に10回以上服用する状態が続くと、薬物乱用性頭痛を引き起こす可能性が高くなります。 いったんそのような状態になると離脱するのが難しくなりますので、そうなってしまう前に予防薬の服用を積極的に検討するべきです。
これまでの片頭痛予防薬は、もともと他の目的で発売されている薬です。降圧薬、抗てんかん薬、抗うつ薬、漢方薬などです。あとから片頭痛への保険承認が降りたものもあれば厳密には保険適応外の薬もありますが、副作用についてはよく知られているので安心して使えます。
2021年には、新しい片頭痛予防薬が次々と発売されました。まとめてCGRP関連予防薬と呼ばれます。抗CGRP抗体薬のエムガルティ®、アジョビ®、抗CGRP受容体抗体のアイモビーグ®の3剤です。
抗CGRP抗体薬は、片頭痛の原因となるCGRPという物質に結合することによって、CGRPが伝達物質としての役目を果たせなくする薬です。抗CGRP受容体抗体は、神経末端のCGRP受容体(受け皿のようなもの)に結合してCGRPを受け取れなくする薬です。
いずれも皮下注射で投与します。従来の予防薬を服用してもなお1ヶ月のうち平均4回以上片頭痛発作がある方が対象となります。高額な薬ですが、承認前の治験や発売後の市場調査の結果を見ると非常に高い効果があります。 また、全身的な副作用はほとんどなく内服薬との競合もなく併存症をお持ちの方にも安心して使える注射薬です。 抗CGRP抗体薬と抗CGRP受容体抗体とでは作用機序は異なるのですが、これまでの臨床試験の結果では効果はほぼ同等です。
これまでの片頭痛予防薬
| 降圧薬 (ミグシス®・テラナス®・インデラル®など) |
片頭痛の起こる最初の血管収縮を抑える目的で使用されます。 |
|---|---|
| 抗てんかん薬 (デパケン®・トピナ®・ガバペン®など) |
片頭痛が三叉神経を刺激するということから神経の刺激を弱める目的で使用されます。 一部妊娠中の方は使用できないお薬がありますので注意してください。 |
| 抗うつ薬 (トリプタノール®) |
うつ傾向の有無にかかわらず、セロトニンの濃度を増やすことで片頭痛の予防効果があります。 低用量で使いますので副作用は少ないです。 |
| 漢方薬 (呉茱萸湯、桂枝人参湯、釣藤散、五苓散など) |
上記の薬との併用が可能です。 |
新しい片頭痛予防薬(CGRP関連薬)
| 商品名 | エムガルティ® | アジョビ® | アイモビーグ® |
|---|---|---|---|
| 原理 |
CGRPに結合してCGRPを無力化します |
CGRPの受容体に結合してCGRPを作動不能にします (抗CGRP受容体抗体薬) |
|
| 使用方法 | 初月は2本/月を注射します。 その後は1本/月の注射です。 |
4週間ごとに1本注射します。 又は、12週間ごとに3本注射します。 |
4週間ごとに1本注射します。 |
| 1本あたり の単価 |
42,638円/本 ※3割負担の場合:12,791円/本 |
39,064円/本 ※3割負担の場合:11,719円 |
41,356円/本 ※3割負担の場合:12,408円/本 |
| 副作用 |
|
|
|
緊張型頭痛
頭や首、肩の筋肉の緊張・収縮が原因で起こる頭痛です。ほとんどの方が一度は経験する頭痛です。
身体的・精神的なストレスが複雑に絡み合って発症すると考えられています。そもそも頭は重いものでありそれを支えている首や肩には負担がかかっています。長時間の同じ姿勢による首や肩の筋肉の緊張が過度に強い状態が続くと、筋肉の血流が悪くなり乳酸などの疲労物質がたまり神経を刺激して痛みを引き起こします。
眼精疲労による筋肉の緊張の高まりも同じような痛みをもたらします。
身体的なストレスはなくても、過度の精神的なストレスなどにより精神的に緊張した状態が続くと自律神経に影響を及ぼして脳の痛みを感知するシステムが機能不全を起こして頭痛を引き起こします。
緊張型頭痛では、締め付けられるような痛みや、首・後頭部の鈍痛・立ち眩みやめまい・吐き気などが伴います。嘔吐を伴うことは通常ありません。頭痛は数時間~数日間続く場合もあれば、慢性化してほぼ毎日続くこともあります。
緊張型頭痛が片頭痛の発症のきっかけになることもあります。
非薬物療法
まずは身体的・精神的ストレスを解消するように努めましょう。リラックスすることが大事です。筋肉の緊張をほぐすストレッチ、体操やスポーツなどの運動も回復に有効です。それだけでは改善が難しい場合には、筋肉を柔軟にする内服薬や血行を促す内服薬を使って治療します。
薬物療法
緊張型頭痛急性期の薬物療法としては、鎮痛剤の服用が有効とされます。 頭痛が起こる頻度が月に数回程度の方は、アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬などの鎮痛剤で症状緩和を図ります。
また、執拗に持続する慢性緊張型頭痛の場合は、筋弛緩剤や抗うつ薬などを用いて治療を行います。
抗うつ薬
| トリプタノール®(アミトリプチリン) | 予防療法としては、もっとも高い有効性があり、第一選択となります。 セロトニン濃度を高めることによって、疼痛抑制系を活性化する作用があります。 抗うつ薬ですが、低用量で使用することにより、うつ状態の有無にかかわらず効果があります。 |
|---|---|
| ミルタザピン®(レメロン) | セロトニン・ノルアドレナリンの効果を高める作用のある抗うつ薬です。 |
筋弛緩剤
| テルネリン®(チザニジン) | 中枢性の筋弛緩薬、つまり筋肉の緊張を緩和させる薬です。 脊髄内の神経経路に作用します。 ミオナール®よりも筋弛緩作用は強いとされていますが、眠気も出やすい薬です。 自動車の運転や仕事などへの影響には注意が必要です。 (注) 抗うつ薬ルボックス®(フルボキサミン)や抗菌薬のシプロキサン®(シプロフロキサシン)と併用禁忌です。 |
|---|---|
| ミオナール®(エペリゾン) | テルネリン®と同じく、中枢性の筋弛緩薬です。 |
| リンラキサー® | 筋弛緩剤・頚肩腕症候群の病名で保険適用されます。 |
漢方薬
|
釣藤散 |
慢性緊張型頭痛に有効です。慢性的に続く頭重・高血圧傾向の頭痛に使用されます。 |
|---|---|
|
葛根湯 |
かぜによく用いられますが、緊張型頭痛、肩こりにも効果があります |
群発頭痛
目がえぐられるような激しい痛みが起こります。20~40歳台の男性に多い頭痛です。片側の目のくぼみからこめかみにかけて痛みます。その他、涙や目の充血・鼻水などの症状を伴うことがあります。3大疼痛のひとつとされていて、目がキリでえぐられるようだと例える人もいます。
原因は、顔面や頭部の感覚をつかさどる三叉神経の働きが過剰に興奮することにより副交感神経系が活性化されて、片側の目の周りの激しい痛みの他に、鼻水や鼻づまり、眼球結膜の充血、涙が出る、まぶたが張れる、瞳孔が縮小するといった症状を伴います、と考えられています。
男性に多く見られる特徴があり、喫煙や飲酒などが誘発要因となります。
一度発症すると、1~2カ月間程続き、痛みが治まってからまた半年から数年経過後に同じような痛みが起こります。
国際頭痛分類では、三叉神経・自律神経性頭痛(TACs: Trigeminal autonomic cephalalgias)の一つとされています。
治療は、トリプタン製剤の他に高濃度の酸素吸入も有効とされています。2018年より自宅での在宅酸素療法が保険適用されました。
群発頭痛の薬について
群発頭痛は、頭痛発作の持続時間が短いため、通常の内服薬では効果を得られません。イミグラン®注射剤(皮下注)は有効です。他のトリプタン製剤も有効性はあると報告はされていますが、本邦では群発頭痛には保険適用がありません。頭痛予防薬としては、ワソラン®、ステロイドなどの有効性も報告されていますが、副作用もあるので内服には注意が必要です。
二次性頭痛
二次性頭痛の原因となる主な脳疾患は、以下の通りです。
くも膜下出血
脳を覆っているくも膜の下で、太い血管が破裂し血が溜まっている状態です。主な症状は、突然頭部を殴られたような強い痛みが現れます。それに伴って、嘔吐・吐き気・意識障害が起こります。中高年の方のくも膜下出血のほとんどは、脳動脈瘤の破裂が原因とされています。
この場合、速やかに処置を受けないと再度脳動脈瘤の破裂を起こして、出血する恐れがあります。命に関わる危険があるので、すぐに救急医療機関を受診しなくてはいけません。
若年者の場合は、脳動静脈奇形やもやもや病が原因となることが多いです。
脳動*離
脳動脈解離が起こった場合、その約60%は椎骨動脈に発症します。また、脳動脈の内膜と中膜間で動脈解離が起こると、脳梗塞を引き起こしてしまいます。一方、中膜と外膜間で動脈解離が起きた場合は、解離性椎骨動脈瘤となってこれが外に破れるとくも膜下出血となります。椎骨動脈解離は、40歳前後の男性に多く見られ、動脈硬化などがない方に多い傾向があります。初期の主な症状は、後頭部に痛みが現れます。このような症状がある場合は、くも膜下出血や脳梗塞が起きる前に速やかに医療機関を受診してください。
脳出血
脳内の細い血管が破裂して出血しています。脳出血は、適切な治療を受けても生活に支障を及ぼす半身麻痺や言語障害などが残ることがあります。高血圧などの生活習慣病によって、動脈硬化が進むことで発症リスクが高くなります。突然起こる強い頭痛が現れ、出血部位によって、麻痺やしびれ・めまい・吐き気・言葉が出にくいなどの症状があります。
脳腫瘍
脳に腫瘍が出来て、頭痛が起こります。遺伝子変異のほか、高脂肪食や喫煙・ストレスなどが原因となります。腫瘍が大きくなるにつれて、頭痛が強くなります。その他、手足の麻痺・視力障害などが現れます。
薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用性頭痛)
画像診断でみつけられるような脳の異常はありませんが、一次性頭痛に苦しむ方が急性期もしくは対症的頭痛治療薬を過剰に使用することによって生じる慢性化した頭痛です。国際頭痛分類では二次性頭痛の中に分類されています。 1ヶ月に10日以上の頻度で3か月以上そのような内服を続けると陥る可能性が高いと言われています。いったんそのような状態になると、離脱するのは難しいですから、急性期もしくは対症的頭痛治療薬の使用頻度が多い方(月に3-4回以上)は、予防薬の内服を積極的に検討する必要があります。
その他の頭痛
国際頭痛分類では他にも様々な頭痛がありますが、ここであげておきたい頭痛には以下のものがあります。
後頭神経痛
後頭部や側頭部の頭皮の神経がなんらかのきっかけで急に過敏になって起こる頭痛です。首の付け根や後頭部の周囲に、キリキリと刺すような痛みを感じるのが特徴です。痛みの持続時間は長くて数分程度ですが繰り返します。1週間程度で自然によくなることが多いです。髪の毛や頭皮を触ったりすることで痛みが生じることがあります。 帯状疱疹が原因で起きる神経痛と症状が似ていますので、頭皮に変化が起きていないかチェックすることは大事です。 後頭神経痛は、緊張型頭痛と同じく首や後頭部の筋肉の過緊張と関連がありますので、同じ姿勢を長時間続けるようなことは避けましょう。症状としては緊張型頭痛は締め付けられるような痛みで数時間〜数日間症状が続くのに比べて、後頭神経痛は鋭い痛みのことが多く持続時間は数分程度という違いがありますので区別できますが、両方を合併していることもあります。
三叉神経痛
三叉神経は顔(鼻や口の中も含みます)や頭の感覚をつかさどる神経です。三叉神経痛では、何かのきっかけで顔の片側に激痛がはしります。会話をしたり、物を噛んだり、洗顔やひげ剃り、歯みがきなどで誘発されます。 同じく三叉神経が関係している頭痛に、三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)がありますが(群発頭痛はそのひとつ)、ここで述べている三叉神経痛はTACsとは異なる疾患です。 三叉神経痛は、三叉神経の近くの脳血管が神経を圧迫することで引き起こされることがほとんどですが、腫瘍など他の疾患で生じることもありえます。 発作の回数は多く1日に100〜200回になることもありますが、1回あたりの持続時間は、数分の1秒から長くても2分程度です。
帯状疱疹による三叉神経ニューロパチー
水痘(水ぼうそう)が治った後に三叉神経節に潜んでいた帯状疱疹ウイルスが活動を再開することで発症します。 典型的な症状では、耳介の後ろにチクチクと針で刺されたような痛みが出現して徐々に額の方に広がってきます。ほとんどの場合、水疱を伴う赤い発疹も出現してきますが、まれに皮膚症状を伴わない場合もあります(無症状性帯状疱疹)。合併症として角膜炎を引き起こして視力低下が残ることもあります。また皮膚症状が治ったあとも長期間にわたって痛みが続くこともあります。 帯状疱疹の発症率は50歳以上で上昇して、日本人では80歳までに約3人に1人が発症するといわれており、早期の治療とともに発症しないように予防も大切です。 当院では、帯状疱疹を予防するワクチン接種を行っていますので、ぜひご相談ください(自由診療)。
頭痛でお悩みがある場合はご相談ください
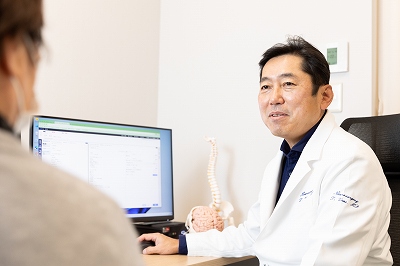 当院では、患者様の頭痛の原因に脳疾患が潜んでいないかを精密に検査できます。脳疾患以外の頭痛に対しても、治療を行っています。頭痛でお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
当院では、患者様の頭痛の原因に脳疾患が潜んでいないかを精密に検査できます。脳疾患以外の頭痛に対しても、治療を行っています。頭痛でお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。