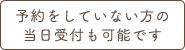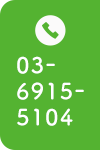めまいとは
めまいは耳・脳・内科疾患・心因性などさまざまな原因で起こります。外来を受診される方の約8割は耳の障害が原因ですが、脳出血・脳梗塞・脳腫瘍など命に関わる病気による場合もあります。
そのため「ただのめまい」と思わず、繰り返す・強い・神経症状を伴うときは早めの受診と精密検査(MRIなど)が重要です。
めまいの症状
めまいの感じ方は大きく分けて3つのタイプに整理できます。症状のタイプによって、耳の異常・脳の異常・循環器や自律神経の問題など原因が異なることがあります。
- 回転性めまい:自分や周囲がぐるぐる回って見える。立っていられないほど強い場合もあり、耳の異常(BPPV、メニエール病など)が代表的。
- 浮遊感・ふらつき:地面がふわふわする、体が揺れるように感じる。耳の障害に加え、脳や心因性のめまいでもみられる。
- 立ちくらみ様めまい:急に立ち上がったときに目の前が暗くなる、気が遠くなる。自律神経の不調(起立性調節障害・血管迷走神経反射)や循環器疾患が関与する。
このように「ぐるぐる回る」か「ふわふわする」か「気が遠くなる」かの違いが、診断の重要な手がかりになります。
めまいの診察
 問診では、めまいの症状について頻度や持続時間・めまいが起こり始めた時期・きっかけ・症状の変化・既往症・服薬中のお薬・症状のお悩みについて詳しくお伺いしています。
問診では、めまいの症状について頻度や持続時間・めまいが起こり始めた時期・きっかけ・症状の変化・既往症・服薬中のお薬・症状のお悩みについて詳しくお伺いしています。
めまいの症状以外に、耳鳴りや難聴などの有無・眼球の動きなどを確認します。
問診および神経学的診察に加えて、当院では重心動揺計グラビコーダを導入して診断の補助としています。重心動揺計では健常値データ200人分を内蔵しており、人工知能解析技術によって「健常」・「異常」(末梢性と中枢性どちらがより疑われるか)を自動判定します。
総合的な診察の結果、脳疾患が原因である可能性を除外する必要ありと判断した場合は、MRI検査を行います。
めまいの原因
まずは全体像
めまいの原因は大きく①耳(末梢前庭)、②脳・神経(中枢)、③循環・内科、④心因・その他に分けられます。外来では耳の原因が約8割ですが、まれに脳卒中など命に関わる病気が隠れることもあります。
見分けのヒント(患者さん用の道しるべ)
- 誘因:頭の向きで悪化 → BPPVなど耳由来/起立・脱水で悪化 → 起立性低血圧・POTSなど
- 耳症状:めまいと同時の耳鳴り・耳閉感・変動する難聴 → メニエール病を考える
- 持続時間:数秒〜1分(姿勢で誘発)→BPPV/数日持続(耳症状なしの強い回転性)→前庭神経炎/10分〜数時間(耳症状あり)→メニエール病
- 神経症状:ろれつ障害・手足のしびれ/脱力・複視・激しい頭痛を伴う → 中枢性(脳)」を最優先に除外
すぐ受診してほしいサイン
- 突然の激しいめまいが持続し、立てない・歩けない
- ろれつが回らない、片側の手足がしびれる/力が入らない、物が二重に見える、強い頭痛
- 新しい難聴や耳鳴りが急に出た/悪化した
以下では、耳の病気(BPPV・前庭神経炎・メニエール病・突発性難聴)を中心に、その後に脳由来・循環/内科・心因性のめまいも解説します。症状が曖昧な場合や中枢性が疑われる場合は、MRI等での評価を行います。
耳疾患によるめまい
平衡感覚を司る耳に障害が起こることで、めまいが生じます。クルクルと目が回るめまいがある場合は、内耳の障害が原因のことが多いです。めまいで受診されるかたの約8割が内耳の障害が原因という報告があります。
良性発作性頭位めまい症(BPPV)
BPPVは耳疾患によるめまいの最も頻度が高い原因で、めまい全体でも大きな割合を占めます。
頭位(頭の向きや姿勢)を変えたときに数秒〜1分程度の回転性めまいが生じ、しばしば吐き気を伴います。多くは後半規管型ですが、外側(水平)半規管型もあります。
原因・タイプ
- 内耳の耳石がはがれて半規管内に入り込むことで発症(耳石置換で改善)。
- 浮遊耳石(canalithiasis):めまいは数十秒で減衰するのが典型。
- クプラ結石(cupulolithiasis):めまいが比較的持続しやすい。
- リスク因子:加齢、女性、片頭痛、頭部外傷、骨粗鬆症、前庭神経炎の既往、糖尿病、長期臥床など。
診断(ベッドサイドで判定)
- Dix–Hallpike 試験(後半規管型)で誘発性めまいと特徴的眼振。
- 仰臥位ロール試験(外側半規管型)。
- 持続性の垂直性眼振や神経症状を伴う場合は中枢性めまいを精査(MRI 等)。
治療(第一選択は耳石置換法)
- Epley 法(後半規管):短時間で高い有効性。
- Semont 法(後半規管):可動制限があっても行いやすい場合あり。
- Barbecue roll(Lempert)法 / Gufoni 法(外側半規管)。
- 自宅ではBrandt–Daroff 体操を指導することがあります。
- 制吐薬などの前庭抑制薬は原則長期連用しない(急性悪心時の短期のみ)。
- 耳石置換後の厳格な体位制限は必須ではないとする報告が主流です。
経過・再発
- 多くは数日〜数週間で改善。再発は比較的多く、数か月〜数年で再発することがあります。
- 再発時も耳石置換で改善が期待できます。繰り返す場合は生活指導とセルフエクササイズを併用。
受診の目安
- めまいが数分以上持続する/歩けない、ろれつ困難、手足の麻痺・しびれ、複視など神経症状を伴う。
- 新規の難聴・耳鳴りを合併する、激しい頭痛を伴う。
前庭神経炎
前庭神経炎はウイルス感染や炎症によって前庭神経が急性に障害されることで起こる疾患です。
突然発症する激しい回転性めまいを主症状とし、数時間でピークに達し、数日〜1週間強く続くのが典型です。吐き気・嘔吐を伴うことが多く、難聴や耳鳴りを伴わないのが特徴です。
症状
- 突然の激しい回転性めまい(歩行困難や転倒を伴うこともある)
- 悪心・嘔吐を伴いやすい
- 耳鳴り・難聴は伴わない(伴う場合は突発性難聴やメニエール病を考慮)
- 眼振は水平性または回旋性で、健側へ向かう
- 症状は数日で改善に向かうが、浮遊感や不安定感が数週間〜数か月残ることがある
診断
- 問診と神経学的診察が基本。持続性の回転性めまい+耳症状なしが特徴。
- Head impulse test(頭部衝撃試験)陽性が診断の手がかり。
- MRIで脳梗塞・脳出血など中枢性疾患を除外することが重要。
治療
- 急性期:制吐薬(メトクロプラミドなど)、前庭抑制薬(ジフェンヒドラミン、ジアゼパムなど)を短期使用。
- ステロイド全身投与が前庭機能の回復を促す可能性があり、発症早期に検討されます。
- リハビリ(前庭代償の促進):早期からの起立・歩行訓練が有効。自宅での前庭リハビリ(注視訓練・頭部運動)も指導します。
- 長期にわたる薬物依存は代償を妨げるため避けます。
経過・予後
- 多くは数週間〜数か月で自然回復する。
- 後遺症として浮遊感・不安定感が残ることがあり、PPPDへ移行する例もあります。
- 再発はまれですが、反対側の前庭神経で起こることもあります。
受診の目安
- ろれつ障害・手足のしびれ・麻痺・複視など神経症状を伴う場合は、脳卒中を否定できないため救急受診が必要です。
メニエール病
メニエール病は、内耳にリンパ液が過剰に貯留(内リンパ水腫)することで発症する疾患です。
めまい・耳鳴り・耳閉感・変動する難聴を繰り返すのが特徴です。働き盛りの30〜50歳代に多く、ストレスや過労、不規則な生活が誘因になることがあります。
症状
- 突然始まる回転性めまい発作:数十分〜数時間(通常10分以上、12時間以内)続く。
- めまいに伴って耳鳴り・耳閉感・難聴が同時に悪化する。
- 発作を繰り返すごとに、次第に難聴が進行・固定化することがある。
- 吐き気・嘔吐を伴うことも多い。
診断(日本めまい平衡医学会基準)
- めまい発作が反復(10分〜数時間)。
- 発作時に蝸牛症状(耳鳴・耳閉感・難聴)を伴う。
- 聴力検査で感音性難聴(低音障害型〜混合型)を確認。
- 中枢性疾患や他のめまい疾患を除外できる。
原因・誘因
- 内リンパ水腫が病理学的所見として確認されている。
- ストレス・睡眠不足・過労・天候変化が誘因となる。
- 遺伝的素因や自己免疫的要因が関与するとする説もある。
治療
- 生活指導:十分な睡眠、規則正しい生活、ストレス軽減、過労回避。
- 食事療法:減塩(1日6g未満が目安)、カフェインやアルコールを控える。
- 薬物療法:利尿薬(イソソルビドなど)、前庭抑制薬、循環改善薬、ビタミン剤など。
- 発作時:制吐薬や鎮静薬を短期的に使用。
- リハビリ:平衡訓練で代償を促進。
- 難治例では内リンパ嚢開放術や鼓室内ステロイド注入などの手術・処置を検討。
経過・予後
- 発作は数日〜数週間で繰り返すことが多い。
- 長期的には難聴が進行し、両側性に移行する例もある。
- 適切な生活習慣の管理と治療で発作頻度を減らすことが可能。
「めまい+耳鳴り・耳閉感・難聴」が同時に出るのがメニエール病の特徴です。
症状があるときは、早めに耳鼻科または神経内科での評価を受けることをおすすめします。
突発性難聴
耳鳴りや耳閉感・難聴などの症状を伴うめまい発作には、突発性難聴という疾患もあります。突発性難聴では、めまい発作は繰り返さないので、同じく難聴を伴うメニエール病との鑑別ができます。逆に言うと、初回の発作では、メニエール病と突発性難聴とは区別が難しいです。
突発性難聴は、症状が出てから約1週間以内に適切な処置を行わないと完治できないことがあるため、速やかに受診する必要があります。治療は耳鼻咽喉科での専門治療が必要になるので、連携医療機関をご紹介いたします。
4疾患の鑑別ポイント
| 疾患 | めまいの特徴 | 耳症状 | 持続時間 | 発症経過 |
|---|---|---|---|---|
| 良性発作性頭位めまい症 (BPPV) |
頭の位置変化で誘発/回転性 | なし | 数秒〜1分程度 | 繰り返す/再発しやすい |
| 前庭神経炎 | 突然の強い回転性めまい/持続 | なし | 数日〜1週間強く続く | 感染後に急性発症/一過性 |
| メニエール病 | 回転性めまい/発作を反復 | あり(耳鳴・耳閉感・変動する難聴) | 10分〜数時間 | 反復し徐々に難聴が進行 |
| 突発性難聴 | めまいを伴うことあり | あり(急な難聴・耳鳴) | めまいは一過性/反復しない | 急激に発症し再発は稀 |
※「めまいだけか」「耳症状を伴うか」「持続時間」「繰り返すかどうか」が鑑別のポイントです。症状が曖昧な場合は、中枢性疾患との鑑別のためMRI検査が重要です。
脳疾患によるめまい
脳幹・小脳の障害によってめまいが起こります。頻度としては耳疾患によるめまいと比べるとずっと低いのですが、なるべく早く適切な治療を開始しなければ後遺症が残ることがあるので、診察時には常に可能性を考えておかなくてはいけません。主に、浮遊感やふらつき・動揺感などのめまい症状が現れます。脳疾患によるめまいが否定できない場合は、かならずMRI検査を行い危険なめまい症状を見逃さないようにしています。
脳出血・脳梗塞・脳動脈解離・脳腫瘍・脊髄小脳変性症など
浮遊感やふらつき・動揺感などに加えて、真っすぐ歩けない・立っていられない・ろれつが回らないなどの麻痺症状がある場合は、脳出血・脳梗塞・脳腫瘍・脳動脈解離・脊髄小脳変性症などの可能性が考えられます。
持続性知覚性姿勢誘発めまい(Persistent Postural Perceptual Dizziness: PPPD)
PPPDは2017年に国際的に定義された新しい慢性めまいの疾患概念で、これまで原因不明とされていた慢性的なめまいの多くを説明できるようになりました。 良性発作性頭位めまい(BPPV)や前庭神経炎などの急性めまいがきっかけとなって発症することが多く、症状が落ち着いた後もふらつきや浮遊感が3か月以上続くのが特徴です。
主な症状
- フワフワした浮遊感や不安定感が慢性的に続く
- 立位・歩行・頭や体を動かしたときに強くなる
- スーパー・駅・人混み・PCやスマホの画面など視覚刺激で悪化
- めまいの強さは日によって変動し、疲労・不安・緊張で悪化しやすい
原因・メカニズム
- 急性めまい後に、脳が過度にバランスを意識する状態が固定してしまう
- 前庭系(平衡感覚)・視覚・体性感覚の情報処理がアンバランスになる
- 不安傾向やストレス、心身の緊張が悪循環を強める
診断
- 3か月以上続く非回転性の慢性めまい
- 立位・動作・視覚刺激で悪化
- 耳鼻科検査・画像検査では明らかな異常が見つからない
- 国際めまい平衡医学会の診断基準(Bárány Society, 2017)を満たす
治療
- 前庭リハビリテーション:頭や体を動かす訓練で脳の適応を促す
- 薬物療法:SSRIやSNRIなど抗うつ薬が有効とされる(少量から開始)
- 認知行動療法(CBT):不安や過敏な注意を修正し、症状軽減につなげる
- 急性めまいで使う前庭抑制薬は長期には無効で、むしろ回復を妨げるため使用しない
経過・予後
- 治療により症状は改善可能。早期に介入するほど良好
- 慢性化しても生活指導・薬物・リハの併用で多くの方が軽快する
- 不安・うつ傾向への対応も再発防止に重要
PPPDは「気のせい」ではなく、脳の情報処理のバランスが崩れていることによる症状です。
当院では前庭リハビリや薬物療法を組み合わせ、必要に応じて心身のサポートを含めた総合的な治療を行っています。
前庭性片頭痛
片頭痛の症状のひとつとして生じるめまいです。国際頭痛分類に独立した疾患群として記載されています。頻度は少ないのですが、認知度が低くこれまで見逃されることの多かっためまいとも言えます。
診断基準では、5回以上の中等度から重度の前庭症状の発作が5分から72時間続くこと、現在あるいは過去に片頭痛の診断基準を満たした頭痛があること、前庭発作の半数以上に片頭痛兆候があることとされています。
詳しくは片頭痛(前庭性片頭痛)のページをご参照ください。
循環器など内科的要因によるめまい
立ちくらみやフラつき、意識が遠のく感じは、血圧・心拍・血糖の乱れで起こることがあります。 放置すると転倒や失神につながることもあるため、原因を見極めて適切に対処します。
起立性調節障害(小児〜若年)/起立性低血圧・POTS(成人)
- 起立性低血圧:立ち上がってから3分以内に収縮期20mmHg以上または拡張期10mmHg以上下がるタイプ。立ちくらみ・視野が暗くなる・失神。
- POTS(体位性頻脈症候群):立位で心拍数が30/分以上増加(思春期〜若年では40/分以上)、血圧は大きく下がらないのに動悸・めまい・倦怠感が続く。
- 若年者では起立性調節障害として、午前中の不調や頭痛、学校生活への支障が目立つことがあります。
ご自宅でできる簡易チェック
- 5分安静で血圧・脈拍を測定 → 立位にして1・3・5分で再測定(安全に注意)。強い症状が出る場合は中止してください。
クリニックでの評価
- 心電図、必要に応じホルター心電図、血圧脈波。
- 臥位・立位での起立試験、必要に応じ耳鼻科や循環器と連携してヘッドアップティルト試験を検討。
対処と治療
-
- 非薬物療法が基本:水分1.5〜2L/日、適度な塩分(他疾患がなければ)、段階的な有酸素運動、ふくらはぎ筋ポンプ運動、弾性ストッキング。
- 起立時はゆっくり立つ、長時間の起立は避ける、下肢交差・握りこぶし法などのカウンタープレッシャー法。
- 必要時、循環器と連携し起立性低血圧に昇圧薬(例:ミドドリン)を使用。
POTSは生活習慣の工夫や運動療法を中心に個別対応し、場合によりβ遮断薬などを検討します。
血管迷走性失神(反射性失神)
- 痛み・恐怖・長時間起立・脱水・排尿後などをきっかけに、ふらつき→吐き気・冷汗→一過性の失神が起こる代表的な良性の失神。
- 前兆(前失神症状)があればすぐ座る・横になる、下肢を高くすることで予防・軽減できます。
- 再発が多い方は、水分・塩分摂取、トリガー回避、カウンタープレッシャー法を習得。稀に薬物療法やペースメーカー適応を循環器と検討。
不整脈(徐脈・頻脈)
- 高度徐脈・房室ブロック・心房細動/粗動・発作性上室性頻拍・心室性期外収縮などで、動悸・めまい・失神が生じることがあります。
- 評価:心電図、ホルター心電図、イベントレコーダー、電解質・甲状腺機能。
- 治療:原因に応じて抗不整脈薬・カテーテルアブレーション・ペースメーカーなどを循環器と連携して行います。
低血糖
- 糖尿病治療中や空腹・過剰飲酒で、冷汗・手の震え・動悸・ぼんやり感から失神へ進むことがあります。
- ブドウ糖摂取で速やかに回復することが多いですが、反復する場合は治療の見直しが必須です。
受診の目安(要注意サイン)
- 胸痛・強い動悸、失神時の外傷、家族に心臓突然死の既往がある。
- 失神が運動中に起きる、前触れがない、回復が遅い、神経症状(片麻痺・ろれつ障害・複視)を伴う。
- 頻回に繰り返す/仕事や学業に支障が大きい。
当院では、神経学的評価に加え、必要に応じて心電図・ホルター・起立試験・血液検査・MRIを組み合わせて原因を丁寧に絞り込み、 循環器・耳鼻科とも連携して治療を進めます。ご心配な方は早めにご相談ください。
頸や腰の筋肉の過緊張によるめまい
身体の平衡機能はきわめて複雑です。皮膚の表在感覚や筋肉や腱などからの深部感覚の情報も平衡感覚には重要です。頚椎症や腰痛などの整形外科的な異常を要因とするめまいもあります。
心因性要因によるめまい
パニック障害・不安障害といった心因性の要因でもめまいは起こります。