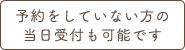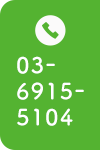頭痛とは(総論)
※このページでは、頭痛の全体像と受診の目安について解説しています。
頭痛は、多くの人が一生のうちに経験する非常に身近な症状です。
実際には、頭痛の多くは命に関わるものではありません。
一方で、頭痛が繰り返し起こる、あるいは長く続くことで、
仕事・家事・学業など、日常生活に大きな支障をきたしてしまう方も少なくありません。
頭痛は大きく分けて、
一次性頭痛(基礎となる病気がない頭痛)と、
二次性頭痛(脳や全身の病気が原因となる頭痛)の2つに分類されます。
一次性頭痛には、片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛などがあり、
命に関わることはほとんどありませんが、適切な治療を行わないと生活の質を大きく下げることがあります。
一方で、頻度は高くないものの、
くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍、感染症など、
早急な対応が必要な病気が原因となる頭痛が含まれることもあります。
そのため頭痛の診療では、
「危険な頭痛ではないか」を適切に見極めることと、
頭痛のタイプに応じた対応を行うことの両方が重要になります。
当院では、脳神経外科専門医が診察を行い、
まず注意が必要な頭痛でないことを確認したうえで、
症状や生活背景に合わせた治療やアドバイスをご提案しています。
こんな頭痛は早めに受診が必要です
頭痛の多くは心配のいらないものですが、
まれに早急な対応が必要な病気が原因となる頭痛があります。
以下は、受診が必要かどうかを判断するための目安です。
当てはまる場合は早めの受診をおすすめします。
- 突然起こった、今までに経験したことのない激しい頭痛
- 数時間〜数日かけて徐々に悪化していく頭痛
- 手足のしびれ・麻痺、言葉が出にくい、視力の異常を伴う
- 意識がぼんやりする、反応が鈍いなどの変化がある
- 発熱やうなじの硬さを伴う頭痛
- 頭部や首を強く打った後に出てきた頭痛
- 50歳以降に初めて出てきた、または様子がいつもと異なる頭痛
これらに当てはまる場合は、
早めの受診が安心につながります。
意識障害や急激な症状の悪化がある場合は、救急要請を優先してください。
よくある頭痛(一次性)
繰り返す頭痛の多くは、以下のような「よくある頭痛」に分類されます。
「自分はどのタイプに近いか」を知ることで、対処や受診の目安が分かりやすくなります。
一次性頭痛とは、頭痛そのものが病気の中心であり、脳や全身に重大な異常がないタイプの頭痛です。
代表的なものに片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛があります。国民の3人に1人が何らかの一次性頭痛に悩まされているとされ、非常に身近な病気です。
もっとも多いのは緊張型頭痛で、肩こりやストレスに伴う鈍い痛みが特徴です。
一方で、医療機関を受診する方の多くは片頭痛(60〜80%)で、強い拍動性の頭痛に加えて吐き気や光過敏を伴い、生活や仕事に大きな支障をきたします。
群発頭痛は比較的まれですが「三大激痛」とも呼ばれ、夜間に眼の奥をえぐられるような激痛発作が周期的に起こる特殊な頭痛です。
このように一次性頭痛は命に関わることはありませんが、繰り返す発作で生活の質(QOL)を著しく低下させるため、適切な診断と治療が重要です。
片頭痛
片側(時に両側)の拍動性の強い痛みに加え、悪心・嘔吐、光や音に敏感になる症状を伴うことが多い頭痛です。 発作は4〜72時間続くことがあり、前兆としてギザギザした光が見える、視野が欠ける、手足がしびれるなどの症状が出る方もいます。 女性に多く、生活や仕事への影響が大きいのが特徴です。
片頭痛は「我慢するしかない」症状ではなく、発症の仕組みが解明されつつあるれっきとした疾患です。 この数年で治療選択肢が大きく広がり、適切に対応すれば生活の質を大幅に改善できます。
片頭痛の原因
脳のリズムを司る視床下部の異常な活性化が引き金となり、三叉神経血管系が刺激され、 CGRPなどの神経ペプチドが放出されることで硬膜周囲に神経原性炎症が起こり、 痛みとして自覚されます。 前兆は後頭葉の神経活動のゆらぎによって生じると考えられています。
片頭痛のネットワークは頭痛に限らず感覚処理や自律神経にも影響します。
そのため典型的な頭痛中心のタイプだけでなく、めまいが主体となる前庭性片頭痛や、 頭痛が出ず前兆症状だけが繰り返される無頭痛性片頭痛といったタイプも起こりえます。
つまり片頭痛は「頭が痛い病気」だけではなく、脳のネットワークの過敏さから多彩な症状を生じる病気と理解すると分かりやすいです。
片頭痛の症状・経過
予兆期:食欲変化・倦怠感・あくび・むくみなどが数日前から出現することがあります。
前兆期:発作の30分〜1時間前に視覚異常(閃輝暗点)、感覚異常(しびれ)、言語障害などが出ることがあります。
頭痛期:拍動性の強い痛みが数時間〜3日続き、悪心・嘔吐、光過敏、音過敏を伴います。
回復期:発作後は眠気や疲労感、気分変化が残ることがあります。
片頭痛の誘因
ストレス・睡眠不足や過多・月経周期・気圧や気温の変化・人混みや強い光/匂い・アルコール・空腹・特定食品(チーズ・チョコレートなど)など。 個人差があるため、自分の誘因を把握することが重要です。
サブタイプ
前兆のある片頭痛/前兆のない片頭痛
片頭痛は大きく「前兆のある片頭痛(migraine with aura)」と「前兆のない片頭痛(migraine without aura)」に分けられます。
前兆のある片頭痛
- 閃輝暗点(ギザギザの光や視野の欠け)が5〜60分かけて進行・消退するのが典型。
- その他、感覚異常(しびれ)、言語障害、運動麻痺などの神経症状が一過性に出現する場合もある。
- 前兆が消失した後に典型的な片頭痛の頭痛が起こる。
- 脳血管障害リスクがやや高いことが知られており、特に若年女性で喫煙+経口避妊薬(低用量ピル)を併用すると脳梗塞のリスクが増えるためエストロゲン含有ピルは禁忌とされています。
前兆のない片頭痛
- 最も多いタイプで、前兆を伴わずに拍動性頭痛や悪心・光音過敏が出現する。
- 診断の中心は発作の繰り返しと症状パターン。前兆がないため見逃されやすく、緊張型頭痛や他の頭痛と区別が必要。
前庭性片頭痛(前庭型)
回転性めまい・ふらつき・動揺視などの前庭症状が5分〜72時間続く発作を反復し、片頭痛の既往や光過敏・音過敏・拍動性頭痛などが随伴します(頭痛が毎回なくても可)。
診断は他の中枢・耳性疾患(脳卒中、メニエール病、BPPVなど)の除外が前提です。治療は片頭痛の急性期治療(NSAIDs/トリプタン/ジタン)+制吐薬を基本に、必要に応じ前庭抑制薬を短期併用。頻発例は予防療法(β遮断薬・抗てんかん薬・CGRP関連薬 など)と前庭リハで再発抑制を図ります。
※めまいが主症状の方は、当院のめまいページの「前庭性片頭痛」もご覧ください
月経関連片頭痛(MRM)
月経周期と関係して起こる片頭痛です。月経開始の2日前〜開始後3日目に発作が集中するのが特徴で、純粋月経片頭痛(この時期にのみ発作)と、月経関連片頭痛(この時期に加えて他の日にも発作)に分けられます。
月経期の発作は強く・長引きやすく・薬が効きにくい傾向があります。
詳細はこちらへ
頭痛発作のない片頭痛(無頭痛性片頭痛)
前兆のみが出現し頭痛を伴わないタイプです。閃輝暗点・感覚異常・言語障害など典型的な片頭痛の前兆症状が繰り返し出現します。
特に中高年以降にみられることがあり、脳梗塞やてんかんとの鑑別が重要です。症状が繰り返される場合は神経内科・頭痛外来での評価が推奨されます。
治療
急性期治療
片頭痛治療は発作時に使う急性期治療と、発作の頻度や重症度を下げる予防治療の二本立てで行います。発作時にはNSAIDs、トリプタン、ジタン(レイボー®)、ゲパント系(ナルティークOD錠)などが使われます。
鎮痛解熱薬(NSAIDs)
アスピリン、イブプロフェン、ロキソプロフェン、ナプロキセンなど。漫然と使うと胃腸障害や腎機能障害のリスクがあり注意が必要です。
片頭痛特異的薬剤
トリプタン製剤は、片頭痛発作時に用いる代表的な治療薬で、三叉神経血管系に作用し、血管収縮作用を介して痛みを抑えます。発作の早い段階で服用することが重要で、心筋梗塞や狭心症などの心血管疾患がある方には使用できない場合があります。
ジタン製剤(レイボー®)は、2022年に登場した新しい片頭痛治療薬で、神経の疼痛伝達を抑制することで効果を発揮します。血管収縮作用を持たないため、心血管リスクのある方にも使用可能です。一方で、眠気やふらつきが出やすく、服用当日の自動車運転や危険作業はできません。
ゲパント製剤(ナルティーク®)は、2025年12月に発売開始となった片頭痛治療薬です。片頭痛に関与するCGRPの働きを抑える内服のCGRP受容体拮抗薬(ゲパント系)で、これまで注射薬が中心であったCGRP関連治療に飲み薬という新たな選択肢をもたらしました。血管収縮作用を持たず、眠気も比較的少ないため、トリプタンやジタンが使いにくい方、あるいは効果が不十分であった方の選択肢となります。また、急性期治療だけでなく発症抑制(予防)にも使用できる点が特徴です。
トリプタン製剤
| イミグラン®(スマトリプタン) |
錠剤・点鼻薬・注射(点鼻は現在日本では入手困難) |
|---|---|
| ゾーミッグ®(ゾルミトリプタン) |
錠剤・口腔内崩壊錠(水なしで飲めるお薬) |
| レルパックス®(エレトリプタン) | 錠剤 *1回1錠:2時間あけて1錠追加可、1回2錠も可で1日最大2錠 早く効いて(1~1.5時間)ゆっくり切れる(1.5~3時間)。 副作用は比較的少ない。授乳中の第2選択肢 |
| マクサルト®(リザトリプタン) |
錠剤・口腔内崩壊錠(水なしで飲めるお薬) |
| アマージ®(ナラトリプタン) | 錠剤 *1回最大1錠:4時間あけて1錠追加可 ゆっくりと効きます(1~3時間)が、長く効く(2~5時間)。 月経関連・持続発作向け、副作用は少なめ(頭頚部圧迫感)。 |
| 特徴まとめ | 速効性:薬剤により差あり(30分~2時間) 再発:比較的起こりやすい(効果が切れると再燃することあり) 運転制限:原則なし(眠気が強い場合は注意) 血管収縮作用:あり(心血管疾患がある場合は使用不可) |
※ マクサルト®(リザトリプタン)および同成分製剤は、 現在全国的に供給が不安定なため、 薬局に在庫がない場合があります。
※ 代替として、他のトリプタン製剤、ジタン製剤、ゲパント系薬剤などから、 症状や体質に応じて選択します。
※ 副作用・注意点
- 最も多い副作用は締め付け感・重感・倦怠感・眠気などで、一般的に一過性です。
- 脳梗塞・狭心症・心筋梗塞などの虚血性脳・心血管疾患の既往がある場合は禁忌です。
- 1種類で効果が不十分な場合は、別のトリプタン製剤への切り替えも検討します。
※ 適応の選択ポイント
- 速効性重視:リザトリプタン、スマトリプタン(注射・点鼻)
- 発作持続が長い/再発が多い:エレトリプタン、ナラトリプタン
- 小児・水分摂取が難しい:リザトリプタンRPD錠、ゾルミトリプタンRM錠
- 妊娠・授乳期:スマトリプタン、エレトリプタン(比較的安全とされる)
ジタン製剤
| レイボー®(ラスミジタン) | 錠剤(1回50mg~200mg適宜増減可、1日最大200mg) 2022年発売の新薬で薬価は高い。 血管収縮作用がなく、心血管疾患や脳血管障害がある患者にも使用しやすい。 5-HT1F受容体作動薬であり、主に神経の疼痛伝達を遮断する。 内服のタイミングが遅れても効果があり、発症から時間が経った片頭痛にも使用可能。 トリプタン無効例にも有効性が報告されている。 副作用はめまい・眠気・傾眠が比較的多く、 服用後8時間は自動車運転や機械操作禁止。 片頭痛発作時のみ使用し、予防には用いない。 |
|---|---|
| 特徴まとめ | 速効性:中等度(内服タイミングが遅れても効果あり) 再発:比較的少なめ 運転制限:あり(服用後8時間は運転・危険作業不可) 血管収縮作用:なし(心血管・脳血管疾患があっても使用しやすい) |
ゲパント製剤(CGRP受容体拮抗薬)
| ナルティーク®(リメゲパント) | OD錠(口腔内崩壊錠) 血管収縮作用がなく、心血管リスクなどでトリプタンが使いにくい方にも選択肢となります。 <急性期治療> 通常、成人には1回1錠(75mg)を片頭痛発作時に内服します。 1日あたりの総投与量は75mgを超えない(原則:同日に追加内服はしない)。 <発症抑制(予防)> 通常、成人には1回1錠(75mg)を隔日で内服します。 【重要】急性期と予防を自己判断で組み合わせず、用法は医師の指示に従ってください。 新薬のため、発売後1年間は予防目的では1回の処方につき最大14日分までの制限があります。 当院では当面、急性期使用としては1処方あたり最大7回分までとして運用します(方針は変更となる可能性があります)。 薬価:2,923.20円/錠 ※3割負担の場合:877円/錠 |
|---|---|
| 特徴まとめ | 速効性:中等度(トリプタンほど即効性はないが安定) 再発:少なめ(CGRP遮断により持続効果) 運転制限:原則なし 血管収縮作用:なし |
予防療法
月に3〜4回以上の発作がある場合や重症例、薬の使い過ぎで頭痛が悪化するリスクがある場合には予防療法を行います。従来の降圧薬・抗てんかん薬・抗うつ薬・漢方薬に加えて、CGRP関連薬(注射薬)が2021年以降日本でも使用可能となりました。さらに2025年からは、経口CGRP受容体拮抗薬(ゲパント系:ナルティーク®)も導入され、予防治療の選択肢が広がっています。
CGRP関連薬は、従来薬で効果不十分な方に特に有効で、副作用が少なく併存疾患があっても使いやすいのが特徴です。投与対象は「少なくとも1種類の予防薬で効果不十分」かつ「月4日以上の片頭痛日」がある場合が目安とされています。
これまでの片頭痛予防薬
| 降圧薬 (ミグシス®・テラナス®・インデラル®など) |
ミグシス®(ロメリジン)などは片頭痛予防として保険適応(〇)があります。 β遮断薬(インデラル®など)は保険適応外(△)ですが、国内外で有効性が確立しており、 臨床現場では広く用いられています。 血管反応の調整や神経細胞の興奮抑制を通じて予防効果を発揮します。 |
|---|---|
| 抗てんかん薬 (デパケン®・トピナ®・ガバペン®など) |
デパケン®(バルプロ酸)などは片頭痛予防として保険適応(〇)があります。 トピナ®(トピラマート)やガバペン®は保険適応外(△)ですが、 神経の過剰な興奮を抑える作用から、症例により使用されます。 妊娠の可能性がある方では使用できない薬剤があるため注意が必要です。 |
| 抗うつ薬 (トリプタノール® など) |
低用量で使用し、セロトニン系を調整することで片頭痛の予防効果を示します。 筋緊張性頭痛を伴う場合や、睡眠障害・抑うつ傾向がある症例で特に有用です。トリプタノール® のみ片頭痛予防として保険適応(〇)があります。 |
| 漢方薬 (呉茱萸湯、五苓散、桂枝人参湯、釣藤散など) |
体質や症状に応じて選択され、他の予防薬との併用も可能です。いずれも片頭痛予防として保険適応(〇)があります。 |
※〇/△は保険診療上の一般的な位置づけの目安です。最終的な処方は症状、併存疾患、既往歴などを考慮して医師が判断します。
※ 漢方薬の特徴と選択のポイント
- 呉茱萸湯(ごしゅゆとう)
冷え症で、手足が冷たく、頭痛がズキズキ強く、吐き気を伴う方に向いています。
月経関連片頭痛や、慢性的な片頭痛に用いられることがあります。 - 五苓散(ごれいさん)
低気圧や天候の変化で頭痛が悪化する方、むくみ・水分バランスの乱れがある方に向いています。
頭重感やめまいを伴う場合にも使われます。 - 桂枝人参湯(けいしにんじんとう)
冷えや胃腸虚弱があり、疲れると頭痛が出やすい方に向いています。
ストレスや体調不良をきっかけに起こる頭痛に用いられます。 - 釣藤散(ちょうとうさん)
肩こりや首こりを伴う頭痛、血圧が高めの方、頭が重い・ぼーっとするタイプの頭痛に向いています。
中高年の方の慢性頭痛で選択されることがあります。
※漢方薬は体質や症状の組み合わせによって選択します。効果には個人差があり、他の予防薬と併用することも可能です。
経口CGRP受容体拮抗薬(ゲパント系)
| ナルティーク®(リメゲパント) | 隔日内服による片頭痛予防が可能な経口薬です。OD錠で服用しやすく、注射薬に抵抗がある方の選択肢になります。 用法(予防):通常、成人には1回1錠(75mg)を隔日で内服します。 注意:1日あたりの総投与量は75mgを超えない。急性期と予防を自己判断で組み合わせません。 処方制限(新薬):発売後1年間は制度上、予防目的では1回の処方につき最大14日分までです。 薬価:2,923.20円/錠 ※3割負担の場合:877円/錠 |
|---|
CGRP関連薬(注射)
| 商品名 | エムガルティ® | アジョビ® | アイモビーグ® |
|---|---|---|---|
| 原理 |
CGRPに結合してCGRPを無力化します |
CGRPの受容体に結合してCGRPを作動不能にします (抗CGRP受容体抗体薬) |
|
| 使用方法 | 初月は2本/月を注射します。 その後は1本/月の注射です。 |
4週間ごとに1本注射します。 又は、12週間ごとに3本注射します。 |
4週間ごとに1本注射します。 |
| 1本あたり の単価 |
42,638円/本 ※3割負担の場合:12,791円/本 |
39,064円/本 ※3割負担の場合:11,719円 |
38,980円/本 ※3割負担の場合:11,694円/本 |
| 副作用 (主なもの・発現率の目安) |
|
|
|
※掲載の用量・薬価・注意事項は概要です。最終的な用量・適応・禁忌は最新の添付文書と医師の指示に従ってください(更新:2025年9月)。
※アジョビの12週間ごと3本まとめての注射については、当院では初回のみ対応しております。2回目以降は通常の投与方法となります。
予防薬はいつまで使う?
片頭痛の予防薬は一生続ける薬ではありません。症状が安定すれば中止を検討します。
- 最近の考え方では、1年半〜2年ほど継続して発作がしっかり減ってから、減量や中止を試みるのが一般的です。
- 途中で中止すると再び発作が増えることがあるため、十分に安定してから判断します。
- 中止後に再発した場合は、再び予防薬を開始することもあります。
- CGRP関連薬などの新しい予防薬も同様で、長期の効果と安全性をみながら調整します。
- 「やめてもいいのでは?」と思ったときは、必ず主治医と相談して決めましょう。
片頭痛の予防薬そのものに「完治させる力」はありません。
しかし、片頭痛は繰り返し発作を起こしていると脳の「頭痛回路」が学習して起きやすくなることがわかっています(中枢性感作)。
しっかり予防して発作を減らしていると、この頭痛回路の過敏さが落ち着き、体質が変わるように片頭痛が起きにくくなることが期待されています。
このため、一定期間きちんと予防薬を続けることが大切です。
新しい薬(ゲパント系)
2025年、日本でもゲパント系(CGRP受容体拮抗薬)が臨床現場に導入されました。
- リメゲパント(ナルティーク®OD錠):2025年12月16日より発売。OD錠で服用しやすく、片頭痛発作時の急性期治療と発症抑制(予防)の両方に適応(詳細は上記参照)。
- アトゲパント:1日1回の経口投与による予防薬として開発が進んでいます(最新情報は随時更新)。
いずれも血管収縮作用がなく、心血管リスクを持つ患者にも使用しやすい点が特徴です。急性期から予防まで治療選択肢が広がり、片頭痛治療の新時代が期待されます。
月経関連片頭痛(MRM)
月経周期と関係して起こる片頭痛です。月経開始の2日前〜開始後3日目に発作が集中するのが特徴で、純粋月経片頭痛(この時期にのみ発作)と、月経関連片頭痛(この時期に加えて他の日にも発作)に分けられます。
月経期の発作は強く・長引きやすく・薬が効きにくい傾向があります。
対処の基本
- 急性期治療を早めに(痛みが強くなる前):トリプタン/ジタン(レイボー®)+必要に応じて制吐薬、NSAIDs。
- 睡眠・水分・規則的な食事、カフェインの摂り過ぎ回避など誘因対策も併用。
短期予防(ミニ予防)
月経が来そうな2〜3日前から開始し、5〜7日程度内服します(周期が不規則な方はアプリ等で予測を補助)。
- トリプタンの短期投与:例)ナラトリプタン/ゾルミトリプタンを1日1〜2回(医師の指示範囲で)
- NSAIDs:例)ナプロキセンなどを連日投与
※用量・日数は体質や既往症で調整します。自己判断での長期連用は避けてください。
予防療法の検討
- 発作日数が多い/日常生活への影響が大きい場合は、通常の予防薬(降圧薬・抗てんかん薬・抗うつ薬・漢方、CGRP関連薬 など)を検討。
- 月経期以外にも発作が目立つときは、短期予防だけでなく継続的な予防へ切り替えると安定しやすくなります。
ホルモン療法について
- 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬の連続/延長周期法でエストロゲン低下を平準化。
- 前兆がある片頭痛ではエストロゲン含有製剤は原則避けます(年齢・喫煙・血栓リスク要確認)。
- 妊娠希望・授乳中は原則非ホルモン療法を優先します。
セルフケアのポイント
- 周期と頭痛を日記(アプリ)で記録し、予測と短期予防のタイミングを合わせる。
- 寝不足・ストレス・空腹・脱水を避ける。鉄欠乏・貧血の有無もときどきチェック。
片頭痛と日常生活の工夫
片頭痛は生活の中のちょっとした刺激で発作が誘発されることがあります。 薬だけでなく、日常生活を工夫することが再発予防につながります。
生活リズム
- 規則正しい睡眠:寝不足も寝すぎも片頭痛の誘因になります。
- 休日と平日の睡眠・起床時間を大きく変えないようにしましょう。
- 強いストレスやストレスから解放されたときも発作のきっかけになることがあります。
食生活
- 空腹・脱水を避けるため、規則的に水分と食事を摂りましょう。
- チョコレート・チーズ・赤ワインなど、一部の食品が誘因となる場合があります(個人差が大きい)。
- カフェインは適量なら有効ですが、飲みすぎや習慣化は頭痛を悪化させます。
- アルコールは発作のきっかけになりやすいため注意が必要です。
日常環境
- 強い光や騒音、人混みなどを避けるように工夫しましょう。
- 天気や気圧の変化で頭痛が出やすい方は、気象情報を参考に予定を調整しましょう。
- パソコンやスマートフォンの長時間使用は休憩を挟むようにしましょう。
運動とリラクゼーション
- 軽い有酸素運動(ウォーキング・ヨガなど)は頭痛予防に有効です。
- 過度の激しい運動は誘因になることがあるため、自分の体調に合わせましょう。
- ストレッチや深呼吸、瞑想などでリラックスする時間を持つことも大切です。
自分の頭痛日記をつけると、どんな状況で頭痛が起こりやすいかが分かり、 誘因を避ける工夫につながります。当院でも頭痛ダイアリーの活用を推奨しています。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は最も頻度が高い一次性頭痛で、多くの人が一度は経験するといわれています。 首や肩の筋肉の緊張、ストレス、長時間の同じ姿勢などが主な要因です。 痛みは後頭部から頭全体に広がる鈍い締め付け感が特徴で、片頭痛のような強い吐き気は少ないですが、 めまい・立ちくらみ・軽い吐き気を伴うこともあります。
原因・誘因
- 長時間のデスクワーク、スマートフォン操作、読書などによる首肩の筋肉の緊張
- ストレス・不安・抑うつなど精神的要因
- 眼精疲労(視力の不調や不適切な眼鏡の使用など)
- 不規則な生活、運動不足、睡眠リズムの乱れ
- 片頭痛との併発も少なくありません(混合型頭痛)
症状の特徴
- 帽子をかぶったような圧迫感・締め付け感が頭全体または後頭部に出現
- 数時間〜数日続くが、慢性化するとほぼ毎日続くこともある
- 嘔吐は少ないが、軽度の吐き気や集中力低下を伴う
- ストレスや姿勢の影響で夕方に悪化することが多い
治療
治療は生活習慣の見直し+薬物療法で行います。軽症例では生活習慣の改善だけでも改善します。
非薬物療法(第一選択)
- 適度な休憩やストレッチ、温熱療法(蒸しタオル・入浴)で首肩の血流を改善
- 姿勢の改善(デスク環境の見直し、モニターの高さ調整など)
- 軽い有酸素運動(ウォーキング・ヨガ)で筋緊張を和らげる
- リラクゼーション法(深呼吸・瞑想・マインドフルネス)
- 必要に応じて理学療法(マッサージ・理学的リハビリ)
薬物療法
- アセトアミノフェン・NSAIDs:急性期に有効。ただし連用は薬物乱用頭痛のリスクあり。
- 抗うつ薬(アミトリプチリン):慢性緊張型頭痛の第一選択予防薬。疼痛抑制系を活性化。
- 筋弛緩薬(チザニジン、エペリゾンなど):筋緊張を和らげる効果。
- 漢方薬(釣藤散、葛根湯など):体質や随伴症状に応じて併用可能。
生活上の工夫
- パソコン作業は1時間ごとに休憩・ストレッチ
- 睡眠時間を規則的に保つ
- 枕の高さや寝具を見直し、首肩の負担を減らす
- 眼鏡・コンタクトの度数が合っているか確認し、眼精疲労を予防
- カフェインの過剰摂取は避ける(頭痛の悪化や薬物乱用性頭痛のリスクになるため)
緊張型頭痛は片頭痛と誤解されやすい頭痛でもあります。 「吐き気がない」「締め付けられる痛みが毎日続く」といった特徴を踏まえ、適切な診断と治療が重要です。 慢性化すると生活の質が大きく下がるため、自己判断せずにご相談ください。
群発頭痛
群発頭痛は「三大激痛のひとつ」と呼ばれるほど強烈な一次性頭痛で、三叉神経自律神経性頭痛(TACs)に分類される代表的なタイプです。。 20〜40歳代の男性に多く、女性では比較的まれです。 発作は片側の眼の奥からこめかみにかけて目がえぐられるような激痛が起こり、 1回の痛みは15分〜3時間ほど持続します。
症状の特徴
- 強烈な片側の眼窩部・側頭部痛(じっとしていられず歩き回るほどの痛み)
- 同じ側に涙・結膜充血・鼻水・鼻づまり・まぶたの腫れなど自律神経症状を伴う
- 発作はほぼ毎日同じ時間帯(特に夜間〜明け方)に起こることが多い
- 数週間〜2か月ほどの「群発期」に集中して繰り返す
- 群発期が終わると半年〜数年は発作がなくなることが多い
原因
詳細な発症メカニズムはまだ解明途上ですが、視床下部の体内時計の異常と、 三叉神経・自律神経反射の過剰な活性化が関与すると考えられています。 飲酒・喫煙・気圧の変化・強いストレスが誘因となることがあります。
治療
群発頭痛の痛みは非常に短時間でピークに達するため、通常の鎮痛薬では効果がありません。 有効な治療としては以下があります。
- 高流量酸素吸入:発作時に10〜15L/分でマスク吸入。即効性があり安全性も高い。2018年からは在宅酸素療法(HOT)が保険適用となり、自宅でも発作時に使用可能になりました。
- トリプタン皮下注射(スマトリプタン皮下注):発作を速やかに抑えられる唯一の注射薬。内服では効果が間に合わないため注射が基本です。
- トリプタン点鼻薬:注射に比べて作用はやや弱いものの、注射が難しい場合の選択肢となります。ただし、近年は供給が不安定で入手困難な時期があるため、第一選択にはなりにくいのが現状です。
- 予防療法:群発期に入ったらベラパミル(カルシウム拮抗薬)が第一選択。効果不十分ならステロイド短期導入やリチウムなども検討されます。
生活上の注意
- 群発期は飲酒でほぼ確実に発作が誘発されるため禁酒が必須です。
- 喫煙は発症リスクや発作の悪化に関連するため控えることが推奨されます。
- 規則正しい生活と睡眠リズムの維持が予防に役立ちます。
群発頭痛は「頭痛のなかでも特に強烈」かつ「治療法が特殊」な頭痛です。 通常の鎮痛薬で改善しない夜間の激痛や周期的な頭痛がある場合は、 群発頭痛の可能性があります。早めに頭痛専門医へご相談ください。
3疾患の鑑別ポイント
| 疾患 | 痛みの特徴 | 随伴症状 | 持続時間 | 発作頻度・周期 |
|---|---|---|---|---|
| 片頭痛 | 拍動性、中等度〜強度、片側優位だが両側もあり | 悪心・嘔吐、光過敏・音過敏、前兆あり/なし | 4〜72時間 | 月1〜数回、女性に多い |
| 緊張型頭痛 | 締め付け感・圧迫感、両側性が多い、軽〜中等度 | 吐き気は少ない、めまい・倦怠感あり | 30分〜数日(慢性例ではほぼ毎日) | 慢性的に持続/夕方に悪化しやすい |
| 群発頭痛 | 眼の奥をえぐられる激痛、片側限定 | 流涙・結膜充血・鼻閉・眼瞼腫脹など自律神経症状 | 15分〜3時間 | 群発期に毎日/同じ時間帯に発作、数週間〜数か月集中 |
※「痛みの性状」「随伴症状」「発作の持続時間と周期」で3疾患を区別することが重要です。症状がはっきりしない場合は、頭部MRIなどで二次性頭痛の除外が必要です。
三叉神経自律神経性頭痛(TACs:Trigeminal Autonomic Cephalalgias)
概要
三叉神経自律神経性頭痛(TACs)は、片側の激しい頭痛に、 同側の自律神経症状(流涙、結膜充血、鼻閉・鼻汁、眼瞼浮腫、顔面発汗、縮瞳など)を伴う頭痛群であり、 主に視床下部−三叉神経自律神経反射系の異常活性を基盤とする疾患群です。
TACsには以下の4疾患が含まれ、発作の持続時間・頻度・インドメタシン反応性の有無で鑑別されます。
- 群発頭痛(Cluster Headache)
- 発作性片側頭痛(Paroxysmal Hemicrania, PH)
- SUNCT/SUNA(Short-lasting Unilateral Neuralgiform Headache Attacks)
- 片側持続性頭痛(Hemicrania Continua, HC)
本来、一次性頭痛は片頭痛・緊張型頭痛・三叉神経自律神経性頭痛(TACs)の3群に大別されます。 片頭痛や緊張型頭痛に比べてTACsは全体として発症頻度が低い疾患です。ただ、TACsの中では群発頭痛が最も一般的で、他の3疾患はさらにまれです。 そのため本ページでは、まず臨床で遭遇頻度の高い片頭痛(8%)・緊張型頭痛(22%)・群発頭痛(0.5%)について述べたうえで、 TACs全体の位置づけと各疾患の概要をまとめています。
分類はICHD-3(国際頭痛分類第3版)に準拠します。
頻度・有病率(海外データの目安)
代表的な住民ベース研究(ノルウェー全国データ、成人4,316,747人)による1年有病率は以下の通りです(/100,000人)。
| 疾患名 | 1年有病率(/100,000):95%CI | 備考 |
|---|---|---|
| 群発頭痛(Cluster Headache) | 14.6(13.5–15.8) | ノルウェー全国研究(2016–2020) 女性でやや高値の傾向 |
| 発作性片側頭痛(Paroxysmal Hemicrania, PH) | 1.4(1.0–1.8) | 同上 |
| 片側持続性頭痛(Hemicrania Continua, HC) | 2.2(1.8–2.7) | 同上 |
| SUNCT/SUNA | 1.2(0.8–1.4) | 同上 |
補足(群発頭痛のレンジ):レビューでは1年有病率の代表値を約53〜64/100,000、生涯有病率を約124/100,000とする報告が広く引用されています。地域や方法で大きく変動します。
※ 数値は国・診断基準・データ源(健診/保険請求/面接調査)で変動します。本表は「目安」としてご参照ください。
病態生理
TACsは、三叉神経血管系と自律神経系をつなぐ 「三叉神経−顔面神経反射アーク」が異常に活性化することで発作が生じます。 この反射経路は三叉神経脊髄路核(TNC)から上唾液核・翼口蓋神経節を介して涙腺や鼻腺に至るもので、 痛みと同側の流涙・鼻閉などが出現します。
さらに、fMRIやPETによる研究では、発作中に視床下部後部灰白質の過活動が一貫して確認されており、 この領域が発作の発火装置(generator)として機能することが示唆されています。 また、CGRPやVIPなどの神経ペプチドの上昇が報告されており、神経血管性炎症の関与も示されています。
各疾患の特徴と鑑別
群発頭痛(Cluster Headache)
- 持続:15〜180分
- 発作頻度:隔日〜8回/日(発作期に集中)
- 特徴:激烈な眼窩・側頭部痛と焦燥・多動、自律神経症状を伴う。
- PETで視床下部後部灰白質の異常活性を認める。
- 急性期治療:高流量酸素(100% O2 12–15 L/分)、スマトリプタン皮下注。
- 予防治療:ベラパミル第一選択、リチウム・トピナ®・ガラカネズマブ(抗CGRP抗体)など。
発作性片側頭痛(Paroxysmal Hemicrania, PH)
- 持続:2〜30分の短い発作が1日5回以上。
- 特徴:群発頭痛と類似の自律神経症状を伴う。
- 診断の決め手:インドメタシンに完全反応(治療的診断)。
- 機序:視床下部活動+三叉神経血管系の過敏化。
SUNCT/SUNA(短時間片側神経痛様発作性頭痛)
- 持続:1〜600秒程度。SUNCTは数秒〜数十秒と短く、SUNAはやや長い傾向。
- SUNCT:結膜充血と流涙が顕著。SUNA:同様の頭痛だが、自律神経症状(鼻閉・顔面発汗など)は多彩で流涙がない場合もある。
- 頻度:1日数回〜数十回(重症例では100回以上)に達することもある。
- 治療:ラミクタール®が第一選択。トピナ®、バルプロ酸、テグレトール®も有効例あり。
- 難治例では静注リドカインを短期間使用することがある。
- 神経血管圧迫を認める場合、微小血管減圧術(MVD)が有効な症例も報告されている。
片側持続性頭痛(Hemicrania Continua, HC)
- 持続:3か月以上の片側持続性頭痛。
- 増悪時にTACs様自律神経症状を伴う。
- 診断の要点:インドメタシンで完全に消失。
- 画像検査(造影MRI)で二次性を除外する。
各疾患の比較表
| 疾患名 | 発作持続 | 発作頻度 | 自律神経症状 | 治療反応性 |
|---|---|---|---|---|
| 群発頭痛 | 15〜180分 | 隔日〜8回/日(発作期) | 強い(流涙・鼻閉・発汗) | スマトリプタン・酸素・ベラパミル |
| 発作性片側頭痛 | 2〜30分 | 5回/日以上 | 強い(群発頭痛に類似) | インドメタシン完全反応 |
| SUNCT/SUNA | 1〜600秒 | 頻回(数十回/日) | SUNCT:充血・流涙/SUNA:多彩 | ラミクタール®・リドカイン |
| 片側持続性頭痛 | 持続性(3か月以上) | 持続痛+増悪期 | 軽〜中等度(増悪時) | インドメタシン完全反応 |
診断と検査の進め方
- ICHD-3の診断基準に基づき、発作時間・頻度・自律神経症状・インドメタシン反応性を整理。
- 造影頭部MRI(±下垂体・後頭蓋窩)で二次性病変を除外。
- 群発頭痛・発作性片側頭痛・HCでは視床下部の過活動をfMRIで認めることがある。
- 治療抵抗例では神経血管圧迫の有無を3D MRAで評価。
治療戦略のまとめ
各TACsは、神経生理学的には共通する経路を持ちながらも、治療反応性により区別されます。
- 群発頭痛:酸素・トリプタン(急性期)、ベラパミル(予防)。
- 発作性片側頭痛・HC:インドメタシンで完全反応(診断的治療)。
- SUNCT/SUNA:ラミクタール®・リドカイン・トピナ®などの抗てんかん薬。
- 難治例では視床下部深部刺激療法(DBS)や経頭蓋磁気刺激(TMS)が研究段階で試みられている。
病気が原因の頭痛(二次性)
二次性頭痛の原因となる脳疾患のうち、緊急性が高いのは以下の通りです。
こんな頭痛はすぐ受診/救急要請を
- 突然の激しい頭痛(雷鳴頭痛):数秒〜数分でピークに達する痛み
- 神経症状を伴う:ろれつが回らない/手足のしびれ・麻痺/視力異常/けいれん/意識障害
- 発熱+うなじの硬さ、感染症が疑われる頭痛
- 頭・首の外傷後の新しい頭痛、徐々に悪化する頭痛
- 妊娠中・産後の強い頭痛、いつもと様子が異なる頭痛
- がん・免疫不全・抗凝固薬内服がある方の新規の頭痛
- 50歳以降に初発、またはこめかみの痛み・顎のだるさを伴う頭痛
迷ったら早めに受診を。重症の頭痛は時間との勝負です。
くも膜下出血
くも膜下出血は、脳の表面を覆うくも膜と脳の間にある血管が破れることで起こる出血です。 脳動脈瘤(血管のこぶ)が破裂するのが最も多い原因で、命に関わる危険性が高い疾患です。
症状の特徴
- 突然の激しい頭痛(「今まで経験したことのない痛み」「バットで殴られたような痛み」)
- 吐き気・嘔吐
- 意識がもうろうとする、昏睡に至る
- けいれん、手足の麻痺、言語障害などを伴う場合もある
特に発症直後の強烈な頭痛が重要なサインです。数時間から数日かけて悪化する片頭痛とは異なり、数分以内に痛みがピークに達します。
原因
- 脳動脈瘤の破裂(中高年で最多)
- 脳動静脈奇形、もやもや病(若年者に多い)
- 外傷
診断
頭部CTで出血を確認します。CTで出血が明らかでない場合でも、腰椎穿刺で髄液の血性変化を調べることがあります。 出血源を特定するためにMRAや脳血管造影を行い、脳動脈瘤や血管異常を確認します。
治療
- 緊急治療が必要であり、即時に救急搬送されることが重要です。
- 根治治療は脳動脈瘤を閉じる処置:開頭クリッピング術または血管内コイル塞栓術。
- 再出血予防のため、できる限り早期(発症から72時間以内)の処置が推奨されます。
- 治療後も脳血管攣縮(合併症)による脳梗塞の予防と管理が必要です。
予後と注意点
くも膜下出血は死亡率が高く、助かった場合も半数以上で後遺症(麻痺・言語障害・認知機能障害など)が残ることがあります。 しかし、破裂前に脳動脈瘤が見つかれば予防的に治療することができます。頭部MRAなどによる早期発見も大切です。
「突然の激しい頭痛」がある場合は、迷わず救急車を呼んでください。 早期の受診と治療が命を守ります。
脳動脈解離
脳動脈解離とは、脳や首の血管の壁が裂けて、血管の内側に血液が入り込むことで起こる病気です。 血管壁が裂けることで血管が狭くなったり、ふくらんだり(解離性動脈瘤)して、 脳梗塞やくも膜下出血の原因になります。 比較的若い世代(30〜50歳代)に多く見られ、動脈硬化が少ない人にも発症することがあります。
起こりやすい場所
- 椎骨動脈(首の後ろを走る血管):最も多い(約60%)。
- 内頚動脈(首の横〜脳に入る血管):次に多い。
主な症状
- 突然の後頭部や側頭部の痛み(片側性で持続することが多い)
- 脳梗塞による症状:手足のしびれ・脱力・言葉が出にくい・めまい など
- 解離性動脈瘤が破れるとくも膜下出血を起こし、突然の激しい頭痛・嘔吐・意識障害を伴う
原因・誘因
- 特に誘因がない自然発症(もっとも多い)
- 軽い首の外傷や不自然な動き(スポーツ、整体、ヨガなどでの頸部伸展)
- 高血圧や遺伝的要因(結合組織異常など)が関与する場合もある
診断
MRI・MRAやCT血管撮影で、血管の「二重腔」「真腔の狭窄」「解離性動脈瘤」などの所見を確認します。 典型的にはT1強調MRIでの高信号(血腫)が診断の手がかりとなります。
治療
- 脳梗塞を予防するための抗血小板薬・抗凝固薬を使用する(出血リスクがなければ)。
- 破裂のリスクが高い場合や瘤が大きい場合は、カテーテル治療(ステントやコイル)や外科的手術を検討する。
- 多くは数か月で自然に治癒するが、その間は再発防止のため安静と血圧管理が重要。
注意点
脳動脈解離は見逃されやすい疾患ですが、頭痛や首の痛みで発症することが多く、 「いつもと違う突然の強い痛み」「後頭部の持続する痛み」があるときには注意が必要です。 若年者でも脳卒中の原因となるため、早期に画像検査を受けることが大切です。
脳出血
脳出血は、脳内の細い血管が破れて出血が起こる病気です。高血圧などで発症リスクが上がります。突然の強い頭痛や、麻痺・しびれ・ろれつ困難・吐き気・めまいなどを伴うことがあります。
脳腫瘍
脳腫瘍は、脳内の細胞に生じた遺伝子変化により発生します。多くは明確な原因が特定できず、生活習慣との直接的な因果関係は限定的です。頭痛のほか、てんかん発作・手足の麻痺・視力障害・言葉の障害などを伴うことがあります。進行は多様で、画像検査と神経学的評価が重要です。
薬の使いすぎ(薬剤使用過多による頭痛)
どんな頭痛?
もともと片頭痛や緊張型頭痛などがある方が、痛み止めや片頭痛薬を過度に使い続けることで 頭痛が日常的に起きやすくなった状態です。頭痛の土台(一次性頭痛)があるうえに、 薬剤の使い過ぎが“増悪因子”として加わる二次性頭痛に分類されます。
- 痛み止めを飲む回数が増えるほど、次の頭痛が起こりやすい体質に変化
- 「効かないから量や種類が増える」悪循環に陥りやすい
- 背景の一次性頭痛では片頭痛がもっとも多い
発生メカニズム(病態生理)
薬剤使用過多による頭痛(MOH)は、単なる「鎮痛薬の飲み過ぎ」ではなく、中枢神経系の可塑的変化を伴う慢性頭痛性疾患と位置づけられます。 その核心には、下行性疼痛抑制系の機能低下、痛覚過敏(中枢感作)、および神経伝達系の恒常性破綻が関与しています。
専門家向けの説明(クリックする)
① 下行性疼痛抑制系の機能低下
頭痛薬の反復使用により、脳幹の延髄背側縫線核(nucleus raphe dorsalis)および青斑核(locus coeruleus)を中心とした セロトニン作動系・ノルアドレナリン作動系の活動が低下します。 この結果、三叉神経脊髄路核(TNC)への下行性抑制入力が減弱し、疼痛情報が増幅されやすくなります。
特にトリプタン・NSAIDsなどの過剰使用は、セロトニン受容体(5-HT1B/1D)やアラキドン酸代謝経路の調整機構を攪乱し、 ドーパミン系・オピオイド系との神経間相互作用も抑制的に変化します。
② 三叉神経血管系の過興奮とCGRPの過剰放出
反復する急性期薬投与により、三叉神経終末からのCGRP(Calcitonin Gene-Related Peptide)およびSubstance Pの放出閾値が低下します。 この持続的放出は、血管拡張・神経原性炎症を介してTNCニューロンの興奮を促進し、 神経炎症性の正のフィードバックループを形成します。
さらに、TNCや視床でのグリア細胞(アストロサイト・ミクログリア)活性化が報告されており、 IL-1β、TNF-αなど炎症性サイトカインの放出が痛覚過敏を助長します。
③ 中枢感作と構造的脳変化
慢性的な疼痛入力により、視床・前帯状皮質・島皮質・中脳中心灰白質(PAG)において 神経可塑的変化(synaptic plasticity)が生じます。 MRI研究では、MOH患者で扁桃体・視床・前頭前野灰白質の体積変化や、 機能的結合性(fMRI)の異常が報告されており、痛みの感受性が恒常的に上昇しています。
この状態は、一次性頭痛(特に片頭痛)の易興奮性体質を背景としており、 薬剤の過使用がそれを慢性化へと変換する「トリガー」的役割を果たします。
④ ドーパミン・報酬系の関与
オピオイド、バルビツール酸、カフェイン、トリプタンの一部は、 中脳辺縁系(腹側被蓋野:VTA〜側坐核:NAc)を介するドーパミン報酬系を刺激し、 服薬による一時的な「快」体験を強化します。 これが報酬依存性行動を形成し、「頭痛=服薬」という学習が定着します。
近年、MOH患者ではD2受容体のダウンレギュレーションが報告され、 報酬系の機能低下と薬剤依存傾向の神経学的基盤が示唆されています。
⑤ 複合的病態モデル
以上の変化は互いに影響し合い、痛み抑制系の低下 → 痛み入力の過剰 → 神経炎症と感作 → さらなる薬剤使用 → 慢性化という 悪循環を形成します。 MOHはこの神経可塑的悪循環の結果として発現する、可逆的な機能性頭痛疾患と考えられています。
病態の可逆性を得るためには、過量使用薬の離脱+下行性抑制系の再構築(予防薬・リハビリ・行動療法)が必要です。
一般向けのまとめ
薬を長期間使い続けると、脳が「痛みを感じやすい状態」に変わってしまうことがあります。 本来は痛みを抑える役割を持つ神経が疲弊し、逆に痛みを強く感じ取る神経の働きが過敏になります。
さらに、痛みを伝える物質(CGRPなど)が増え、少しの刺激でも頭痛が起きやすくなります。 「飲むと楽になる」経験が繰り返されることで、脳が薬を求めやすくなり、知らないうちに頭痛を悪化させる悪循環に陥ります。
この状態は正しい治療で元に戻すことが可能です。 薬を減らす/止めるときは、医師と相談しながら慎重に進めることで、脳のバランスを少しずつ回復させていきます。
過量使用の目安(参考)
以下のいずれかを3か月以上続けると、薬剤の使用過多による頭痛を来しやすくなります(代表例)。
| 薬の種類 | 1か月あたりの使用日数の目安 | 例 |
|---|---|---|
| トリプタン製剤/エルゴタミン製剤/ 配合鎮痛薬(カフェインや鎮静剤入り)/ オピオイド |
10日以上/月 | スマトリプタン、ゾルミトリプタン等/エルゴタミン配合剤/市販の配合鎮痛薬 等 |
| 単剤の一般的な鎮痛薬(NSAIDs・アセトアミノフェン など) | 15日以上/月 | ロキソプロフェン、イブプロフェン、アスピリン、アセトアミノフェン 等 |
※「月10日以上の頻度が続いているかも…」と感じたら早めにご相談ください。
こんなサインは要注意
- 頭痛の頻度や持続時間が徐々に増えている
- 薬の効きが落ちた/必要量が増えた、種類が増えた
- 「予防のつもり」で発作がない日にも服用してしまう
- カフェイン入りの市販薬をほぼ毎日手放せない
治し方の基本
ポイントは①過量使用薬の中止・減量と②予防療法の導入、③生活の見直しです。 個々の薬や背景疾患によって進め方が異なるため、医師と計画を立てて進めましょう。
① 過量使用薬の中止・減量(離脱)
- トリプタン/NSAIDs/アセトアミノフェン:多くは中止(断薬)が基本。数日〜2週間で離脱症状(頭痛悪化、吐き気、眠気など)が落ち着くことが多い。
- オピオイド/バルビツール酸含有薬:自己中止は危険。必ず医師のもとで漸減(少しずつ減量)。
- カフェイン配合鎮痛薬:カフェイン離脱頭痛を避けるため、段階的に減らす場合があります。
② ブリッジ療法(離脱期のつなぎ)
断薬初期のつらさを軽減するため、短期間だけ使用します(体質や合併症で調整)。
- 消炎鎮痛薬(長時間作用型)を短期で
- 制吐薬(悪心・嘔吐対策)
- 必要に応じてステロイド短期導入 ※長期連用は不可
③ 予防療法の導入・強化
背景にある一次性頭痛(多くは片頭痛)へ、予防薬をしっかり導入することで再発を抑えます。 従来薬(降圧薬・抗てんかん薬・抗うつ薬・漢方)に加え、 CGRP関連薬(注射)は有効性と忍容性のバランスに優れ、薬物乱用からの離脱支援にも役立ちます。
再発予防の「3ルール」
- 急性期薬は月2日/週、合計で月8〜9日以内を目安に(トリプタンは月9日以内)。
- 配合鎮痛薬(カフェイン等)や市販薬の常用を避ける(連日使用はNG)。
- 予防療法+生活の見直し(睡眠・ストレス・脱水/空腹の回避・アルコール控えめ・頭痛日記の活用)。
※「月に3〜4回以上」急性期薬が必要なら、予防療法の見直し時期です。
よくある質問
- 断薬はどれくらいつらい?いつ楽になりますか?
- 個人差はありますが、最初の数日がもっともつらく、1〜2週間で落ち着くことが多いです。ブリッジ療法と予防薬で乗り切ります。
- 職場や家庭の予定があり、断薬のタイミングが心配です。
- 予定の少ない時期や連休を活用し、計画的に実施します。通院間隔を短くし、連絡手段を確保して伴走します。
- 市販薬でも薬物乱用性頭痛になりますか?
- はい。とくに配合鎮痛薬(カフェイン・鎮静成分入り)は依存性や乱用につながりやすく、注意が必要です。
薬の使い過ぎに心当たりがある、あるいは「効かないから量が増えている」場合は、早めにご相談ください。 個々の薬の種類・併存症・お仕事や生活の事情に合わせたオーダーメイドの離脱計画を一緒に作ります。
その他の頭痛
国際頭痛分類では他にも様々な頭痛がありますが、ここであげておきたい頭痛には以下のものがあります。
後頭神経痛
後頭神経痛は、首の後ろから頭頂部にかけて分布する大後頭神経や小後頭神経が圧迫・炎症・刺激を受けることで起こる神経痛です。 電気が走るような鋭い痛みが突然後頭部に出て、数秒〜数分でおさまりますが、繰り返し出現するのが特徴です。
症状の特徴
- 首の付け根から後頭部、側頭部にかけてピリッ・ズキッとした痛み
- 痛みは片側または両側に出る
- 髪をとかす・洗髪・枕に頭をつけるなどの刺激で誘発されやすい
- 痛みは数秒〜数分と短いが、1日に何度も繰り返すことがある
- 後頭部を押すと圧痛があり、痛みが誘発されることもある
原因・誘因
- 長時間の不良姿勢(デスクワークやスマホ操作による「ストレートネック」)
- 肩や首の筋肉の過緊張、慢性的なコリ
- 外傷や打撲による神経刺激
- 頸椎症や頸椎椎間板ヘルニアなど首の病気
- 帯状疱疹後に残る神経障害性疼痛
治療
- 生活習慣の改善:姿勢を正す、長時間同じ姿勢を避ける、ストレッチや温めで筋肉の緊張を和らげる
- 薬物療法:鎮痛薬(NSAIDs)、神経障害性疼痛に有効な薬(プレガバリン、ガバペン®など)、必要に応じて抗うつ薬(アミトリプチリンなど)
- 神経ブロック注射:局所麻酔薬を後頭神経の出口付近に注射すると、痛みが劇的に改善する場合があります
- 外科的治療:ごくまれに、難治例では神経剥離や熱凝固などの専門的治療が行われることもあります
後頭神経痛は緊張型頭痛と間違われやすいですが、鈍い持続痛ではなく刺すような鋭い痛みが繰り返し出るのが大きな違いです。 片頭痛と合併することもあり、正しい診断と治療が重要です。
繰り返す後頭部の電撃痛でお困りの方は、早めにご相談ください。
三叉神経痛
三叉神経痛は、顔の感覚をつかさどる三叉神経が刺激や圧迫を受けて起こる神経痛です。 突然、顔の片側に電気が走るような激痛が生じ、数秒〜2分程度でおさまりますが、1日に何度も繰り返すのが特徴です。
症状の特徴
- 顔の片側に「電撃が走るような痛み」
- 痛みは瞬間的(数秒〜数十秒)だが強烈で、繰り返し出る
- 発作は1日に数回〜数百回に及ぶこともある
- 会話・食事・歯磨き・洗顔・ひげ剃り・風が当たるなど、日常の刺激で誘発されやすい
- 痛みのために食事や会話が困難になることもある
原因・誘因
- 血管による神経圧迫(もっとも多い原因)
- 脳腫瘍や多発性硬化症などによる二次性三叉神経痛
- まれに原因が特定できない特発性もある
治療
- 薬物療法:テグレトール®が第一選択。オキスカルバゼピンやラミクタール®、ガバペン®なども使用されます。
- 神経ブロック:局所麻酔を神経周囲に注射し、発作を一時的に抑えることがあります。
- 外科的治療:薬で十分な効果が得られない場合は、血管が神経を圧迫している部分をはがす微小血管減圧術(MVD)や、放射線治療(ガンマナイフ)、熱凝固などの手術療法が検討されます。
緊張型頭痛や片頭痛との違い
緊張型頭痛は「締め付けられる鈍痛」、片頭痛は「拍動性で吐き気を伴う痛み」であるのに対し、 三叉神経痛は「電撃が走るような一瞬の激痛」が特徴です。 ただし、顔面の痛みを伴う片頭痛や帯状疱疹後神経痛と似ていることもあり、正確な診断が必要です。
顔に繰り返し電気が走るような痛みがある場合は、三叉神経痛の可能性があります。 早めに受診し、適切な治療を受けることが大切です。
典型的な三叉神経痛ではない顔面の痛み
顔の痛みがすべて三叉神経痛の典型像(電撃のような瞬間痛)に当てはまるわけではありません。以下のようなタイプの「非定型顔面痛」も存在します。
持続性顔面痛(非定型顔面痛)
- 顔の片側や広い範囲に鈍い痛み・灼けるような痛みが続く
- 発作性ではなく持続性で、日によって強さが変動する
- 歯科治療や外傷を契機に発症する場合がある
- 三叉神経痛のような「電撃痛」ではないため、診断に時間がかかることもある
持続性片側顔面痛症候群(PIFP)
- 顔の片側に限局する持続的な痛みが3か月以上続く
- 明確な神経圧迫や腫瘍がなく、画像検査で異常が見つからない
- ストレスや心理的要因が関与することもある
治療の考え方
- 鎮痛薬が効きにくく、抗うつ薬(アミトリプチリンなど)や抗けいれん薬(ガバペン®・プレガバリンなど)が用いられる
- 心理的サポートや心身医学的アプローチも有効
- 難治性の場合はペインクリニックと連携して治療を検討
典型的な三叉神経痛でない顔面痛は「診断名がつきにくく、治療に時間がかかる」のが特徴です。
「顔の片側がジクジク痛む」「電撃痛ではないのに痛みが続く」といった場合も、早めにご相談ください。
帯状疱疹による三叉神経ニューロパチー
帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)の原因となる水痘・帯状疱疹ウイルスが再び活動することで発症します。 三叉神経に潜んでいたウイルスが再活性化すると、顔や口の中に激しい痛みが出る「三叉神経ニューロパチー」を起こすことがあります。
症状の特徴
- 顔や頭の片側に強い痛みが出る
- 典型的には水ぶくれを伴う赤い発疹が同じ部位に出る
- 発疹は額・眼の周り・鼻の横・口の中など、三叉神経の支配領域に一致する
- まれに皮疹が出ない(無疹性帯状疱疹)ことがあり、神経痛だけが残る場合もある
- 眼に及ぶ場合は角膜炎や視力障害を起こす危険がある
- 皮疹が治ったあとも長期間の神経痛(帯状疱疹後神経痛)が残ることがある
診断のポイント
特徴的な皮疹があれば診断は容易ですが、無疹性の場合は片側の顔の強い痛みが唯一の手がかりになることがあります。 顔の強い痛みが続くときには、早めの受診が重要です。
治療
- 抗ウイルス薬(アシクロビル、バラシクロビルなど):発症から72時間以内に開始することが最も重要です。
- 鎮痛薬:NSAIDsやアセトアミノフェンのほか、神経障害性疼痛に有効な薬(プレガバリン、ガバペン®など)を使用することがあります。
- ステロイド:重症例で炎症を抑える目的で使われることがあります。
- 眼科的評価:眼に症状が及んでいる場合は、角膜炎や視力障害のリスクがあるため眼科受診が必要です。
予防
帯状疱疹は50歳以上で発症リスクが高まるため、ワクチン接種が推奨されています。現在日本では2種類のワクチンがあります。
- 生ワクチン(従来型):発症を約50%予防。1回接種で済みますが、効果は5年程度で薄れます。
- 不活化ワクチン(シングリックス®):発症を90%以上予防し、帯状疱疹後神経痛の予防効果も高いとされています。2回接種が必要ですが、効果は10年以上持続すると報告されています。
当院でも帯状疱疹ワクチン接種を行っています。
自治体による助成制度が利用できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
顔の強い痛みや発疹があるときは、自己判断せず早めの受診が大切です。 特に目の周囲に発疹や痛みが出た場合は、失明リスクを避けるため早急に眼科との連携が必要です。
可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)
可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)は、脳の動脈が一時的に強く収縮してしまうことで、 突然の激しい頭痛や神経症状を引き起こす病気です。数週間から数か月で自然に回復することが多い一方で、 発症初期にはくも膜下出血や脳卒中と区別が難しく、注意が必要です。
症状の特徴
- 雷鳴頭痛:突然「雷に打たれたような」激しい頭痛。数秒〜数分でピークに達する。
- 頭痛は繰り返して出現する(数日間〜数週間にわたり複数回)。
- 一部の患者では吐き気・嘔吐・視覚異常・けいれん・手足のしびれや脱力などを伴う。
- 妊娠・出産直後や、薬剤(抗うつ薬、トリプタン、違法薬物など)をきっかけに発症することもある。
原因・誘因
- 産褥期(出産後数週間)
- 一部の薬剤(抗うつ薬、偏頭痛治療薬トリプタン、免疫抑制薬など)
- 違法薬物(マリファナ、コカインなど)
- 激しい運動、強いストレス
- ウイルス感染後
診断
画像検査(MRAや脳血管造影)で、複数の脳動脈に「数珠状の狭窄」が確認されます。 発症から3か月以内に自然回復するのが特徴です。 ただし、くも膜下出血や動脈解離など、他の危険な疾患を除外するために精密検査が必要です。
治療
- 多くは自然に改善するため、安静と経過観察が基本です。
- 鎮痛薬で痛みを和らげるほか、カルシウム拮抗薬(ニモジピンなど)が有効とされることがあります。
- 誘因となった薬剤の中止や生活習慣の見直しも重要です。
注意点
RCVSは多くが可逆的に改善しますが、一部で脳出血・脳梗塞を合併することがあります。 「突然の激しい頭痛」「繰り返す雷鳴頭痛」がある場合は、自己判断せず速やかに受診してください。
一次性運動時頭痛
強い運動やいきみ(ランニング・重量挙げ・性行為など)に伴って起こる頭痛で、明らかな脳疾患を伴わないタイプを「一次性運動時頭痛」と呼びます。若年〜中年に比較的多く、片頭痛の素因がある人で発症しやすいとされます。
症状の特徴
- 運動開始中〜直後に発症し、拍動性の強い頭痛。
- 持続は5分〜48時間程度。
- 運動をやめると軽減するが、数時間残ることもある。
- 片頭痛に似て吐き気や光過敏を伴う場合がある。
注意点(鑑別)
初発例や症状が強い場合は、必ず二次性頭痛(くも膜下出血・動脈解離・脳静脈血栓症など)を除外することが大切です。特に「突然の激しい頭痛(雷鳴頭痛)」の形をとる場合は精査が必要です。
治療・予防
- 軽症例ではウォーミングアップを十分に行う、脱水を避ける、過度のいきみを控えるなどの生活工夫で改善することがあります。
- 繰り返す場合はインドメタシンの頓用・予防内服が有効とされます。
- 片頭痛既往がある場合は、片頭痛予防薬が奏功することもあります。
運動時の頭痛は危険な頭痛と紛らわしいため、初めて経験した場合や症状が強い場合は、必ず脳の検査を受けることをおすすめします。
頭痛でお悩みがある場合はご相談ください
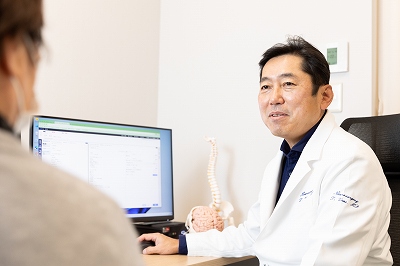 当院では、患者様の頭痛の原因に脳疾患が潜んでいないかを精密に検査できます。脳疾患以外の頭痛に対しても、治療を行っています。頭痛でお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
当院では、患者様の頭痛の原因に脳疾患が潜んでいないかを精密に検査できます。脳疾患以外の頭痛に対しても、治療を行っています。頭痛でお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。